都市間格差の拡大と対策
イノベーション産業を持つ都市は繁栄する一方で、持たざる都市は衰退する。都市間の格差が今後も拡大することを経済理論と実証データにより明らかし、その対策について述べている。
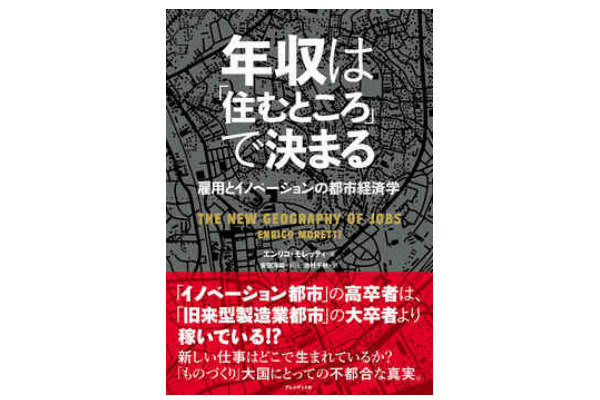
『年収は「住むところ」で決まる 雇用とイノベーションの都市経済学』
著者:エンリコ・モレッティ、安田洋祐(解説)、池村千秋 (翻訳)
出版社:プレジデント社
発売日: 2014年4月23日
イノベーション産業はアメリカの雇用全体に占める割合は低いが、経済の生産性を牽引するため経済成長に大きく寄与している。雇用においても、イノベーション産業の1つの雇用創出が新たに5つの雇用を生むため、地域への波及効果も絶大で一般の製造業の3倍にもなるという。また、そのような産業を持つ都市は雇用や所得、教育、文化、健康、結婚などで住む人に良い影響を与える。
なぜ、シリコンバレーのようなイノベーション産業の集積地ではそのようになるのか。それは「集積効果」により労働市場に厚みが出て、ビジネスインフラが整い、知識の伝搬が促進されるからだ。そして、集積が集積を呼ぶことで一部の地域に極度に集中するのだ。
他方で「集積効果」により企業や高技能労働者の流出が止まらないのがイノベーション産業を持たない都市で、都市間における格差は急速に広がっている。中でも驚きなのがシリコンバレーの高卒者の年収が産業の転換に失敗した都市の大卒者の年収より高いというデータだ。このような二極化がアメリカに分断をもたらしているのだ。
ところで、グローバリズムが雇用を奪ったとする説を耳にするが実際はどうなのか。本書は海外へのアウトソーシングにより製造業では雇用が減少し、イノベーション産業では雇用が増加したことをデータで示している。
中央大学商学部准教授・田中鮎夢氏の研究『第28回「中国の衝撃:中国からの輸入増大がアメリカ製造業に与えた影響」(独立行政法人経済産業研究所 掲載)』によれば、中国からの輸入による製造業の雇用への影響について、アメリカは大ダメージを受けた一方、日本は雇用が増えたという結果もある。
つまり、国際競争力が求められるモノ・サービスは革新的で他に類が無い、簡単に模倣されない性質を持っていないと淘汰されるということだ。
国際競争に敗れた企業が多い都市では衰退に歯止めがかからない状況であるが、復活のためには何とかしてイノベーション産業を持つ都市に変身するしかないのだ。
筆者がイノベーションと格差是正の提言として挙げるのが科学研究と人的資本への投資である。しかし、アメリカではそれが不十分だと嘆く。基礎科学の研究に割り振る政府の予算が減っているが、当然増やすべきであり、社会全体で恩恵をもたらす民間企業の研究開発投資には政府が介入し、投資を促す制度にするべきだと主張する。
賃金格差は大学卒の労働者の需要増に対して、供給が足りないために賃金が押し上げられることで起こっている。大学進学を投資の観点で見た場合に、利回りは大学進学が15%以上、株式投資が7%、債券や不動産投資が3%未満となり、しかもリターンの安定性はかなり高い。教育は公共財であり利回りが絶大なのだから、政府はその投資を抑えるべきではないのだ。
日本も他人事ではいけない。財政健全化の下に科学研究費が年々削減された結果、大学の研究論文の数も減少傾向にある。中長期的な成長の源泉となる投資を抑制することは、未来に大きな禍根を残すだろう。なお、日銀の金融政策の失敗で過度な円高を招いて国際競争力を低下させた時期が長く続いたので、日本の場合は緊縮財政と共に金融政策についても留意すべきだろう。
本書はイノベーションをテーマとして新々貿易理論や労働経済学、教育経済学などの重要な研究結果を分かりやすく説明している。仕事や人生を考える上でも教訓の多い一冊である。(書評ライター 池内雄一)
【編集部のオススメ記事】
・アパート経営の9割は会社員!?サラリーマンが最強な理由とは?(PR)
・佐川急便、親会社が上場申請 3000億円以上の大型案件に
・なんとなくで選んで損してる?自分にあった保険の選び方(PR)
・100万円で79万円儲かる?「究極の」資産運用術とは
・株初心者はどこで口座開設してる?ネット証券ランキング(PR)