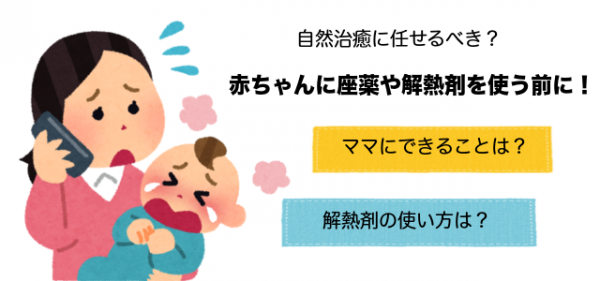
えっ?!さっきまで元気だったのに?!って思うくらいで熱が上がったりすることがあってびっくりします。
でも、いつも元気いっぱいで遊んでいるのに、ぐったりしてツラそうだとかわいそうですよね。
赤ちゃんや小さい子供は自分の状態を言葉で伝えられない分、大丈夫なのかな?って親の心配もふくらみます。
大人だったらこのくらいの熱だとまずいかも!ってわかりますが、赤ちゃんの熱が高いときってすぐに下剤や座薬を使っていいのか、それともあまり使わない方がいいのかどうなんでしょう?!
無理に熱を下げない方が免疫がついて、強い子になるとも聞きますので余計に迷いますよね。
赤ちゃんが熱を出した時どう対処したらよいか、座薬や解熱剤はどう使うのが正しいのかまとめてみました。
目次
赤ちゃんの熱が出たら解熱剤は使わない方がいい?
ポイント
- 体にウイルスや細菌が入ると体温を上げてウイルスを退治しようとします。
- 熱を出すことで体が免疫を獲得していく段階なので解熱剤はむやみに使わない方がいいと言われています。
- 赤ちゃんが苦しがっていたり、眠れない場合は熱をさげるために使用してあげましょう。
- 熱の他に心配な症状がない場合は自然治癒力に頼ってみてもよいでしょう。
お医者さんの中には「解熱剤は使わない方がいい」と言う方がたくさんいます。なぜなら、熱がでるというのは体に入ったウイルスや細菌を死滅させるために必要な反応だからです。
ウイルスや細菌が体に入ると脳から「熱をだす!」という指令が送られます。それによって体が熱を出すんですね。
熱が出ると体の中では次のようなことが起こっています。
- ウイルスや細菌は低温で繁殖しやすいため、体温を上げることで繁殖を防ぐ
- 病原菌をやっつけるために白血球が活発に活動する
- 免疫反応が高まり体に入ったウイルスや細菌を攻撃する
熱を出すことで体がウイルスと戦っているので、むやみに熱を下げるべきではないという考えがあります。解熱剤を使わず自然治癒によって治すことで免疫力が強くなるとも言われています。
赤ちゃんは生後6ヶ月をすぎてくると熱を出すことが増えてきます。これは、ママからもらった免疫が切れてくる時期で自ら免疫力を獲得していく時期だからです。
熱をだすことで免疫力が育っていくので赤ちゃんにとっては成長に必要なプロセスだといえますよね。
自然治癒力に頼っていい時は?
赤ちゃんの免疫力を高めるためにも自然治癒で治してあげたいですよね。では、どんなときであれば自然治癒力に任せる処置をとっても大丈夫なのか見ていきましょう。
熱の高さとともに次の点をチェックします。
・水分をとれるか
・食欲はあるか
・おしっこは出ているか
・お腹が固くないか
問題がなければ自然治癒を考えても大丈夫です。赤ちゃんが熱を出すと心配ですが、まずママは赤ちゃんが持っている自然治癒力を信じて見守りましょう。
必要以上に症状を抑えたりせず、必要なサポートができるようにしておきます。元気そうであれば遊ばせてかまいませんし、無理に寝かせる必要はありません。
自然治癒力に任せる時どうしたらいい?
ポイント
赤ちゃんが熱を出したら自然治癒で治すためにママはサポートしましょう。
- 赤ちゃんを薄着にする
- 部屋の温度は涼しめにする
- 高熱のときは冷やす
- 水分補給はこまめに行う
上記のことに気をつけ、赤ちゃんの自然治癒力を信頼して手を出しすぎず見守りましょう。
続いて、自然治癒力に任せるときにママができることを見ていきましょう。
赤ちゃんを薄着にする
赤ちゃんは温めすぎてしまうと熱性けいれんを起こしてしまうことがあります。熱が上がるときは寒気を感じるので服や布団で温めてあげ、熱があがりきったら服は着込ませすぎずできるだけ薄くしてあげましょう。熱が上がりきったのに温め続けてしまうと、熱がさらにあがるだけでなく体力も消耗してしまいます。
部屋の温度は涼しめにする
部屋が暑すぎると体にも熱がこもってしまいます。夏場はクーラーを少し涼しめに設定します。冬は暖房の温度を少し下げたり、こまめに窓を開けて換気するようにしましょう。熱がでているときは咳や鼻水などの症状も出ていることがあります。その場合は、部屋を加湿器などでしっかり加湿してあげましょう。
高熱のときは冷やす
熱38.5度以上になったら頭を冷やしましょう。冷やすのは後頭部や首の後ろなど脳へ行く血液です。冷却シートなどを頭に張るのは気持ちがいいですが血液を冷やす効果を過信しすぎないようにしましょう。39度を超えるときは脇の下や背中、足の付け根などリンパや太い血管のある場所を冷やすとよいでしょう。
水分補給はこまめに行う
熱がでたときに怖いのは脱水症状になることです。ですので、ママはこまめに水分補給をしてあげましょう。母乳の赤ちゃんは母乳を飲ませます。その他にも水やお茶、赤ちゃん用のイオン飲料などを飲ませましょう。大人用のイオン飲料は甘過ぎますので、赤ちゃん用をあげましょう。赤ちゃんの唇が乾いてきたときが水分不足のサインです。
病院へいくタイミングは?
自然治癒で治すために見守っていても、赤ちゃんの症状が変化することがあります。症状の変化や自分で判断できない場合は、小児救急電話相談で相談したり、こどもの救急などで受診の目安を見てみるとよいでしょう。
ただし、赤ちゃんの様子が変化したときや次のような症状が現れたときは病院を受診してください。もし、意識がないほどぐったりしている場合はすぐに救急病院にいってください。
・不機嫌
・水分をとらない
・食欲がない
・けいれんをおこした
・下痢や嘔吐がある
普段からかかりつけの小児科や夜間の救急の連絡先などを目につく場所に張っておきましょう。
解熱剤とは?
ポイント
「解熱剤」とは熱を下げるための薬で、座薬や粉・シロップ・錠剤などがあります。
赤ちゃんに使うのは座薬が一般的です。
【座薬のメリット】
- 効果が早い
- 規定量を吸収することができる
- 冷蔵保存できる
【座薬のデメリット】
- 挿入を嫌がることが多い
- 腸が荒れることも
座薬は熱が38.5度以上でぐったりしていたり、苦しそうなときに使用します。熱が高くても元気だったり食欲がある場合は使わなくてもよいでしょう。
熱が高い場合、病院を受診すると解熱剤を処方されます。
解熱剤とは熱を下げるための薬です。解熱剤には座薬や粉、シロップ、錠剤などもあります。赤ちゃんに使用する解熱剤で代表的なものは肛門から挿入する座薬です。
熱が出て病院を受診すると「熱が上がったときのために座薬を出しておきます」と処方されますが、必ず使わなくてはいけないわけではないんです。
少し熱がでたくらいで座薬を使うのは逆におすすめできません。赤ちゃんや子供の状態を見て熱を下げた方がよいときに座薬を使います。
座薬のメリットは?
効果が早い
肛門から入った薬は直腸で溶け吸収されるので、飲み薬よりも効き目が早いです。赤ちゃんの高熱が続く場合、体力を消耗したり脱水症状になる危険があります。そんなときにすぐに熱を下げてくれる座薬は心強いですよね。
規定量を吸収することができる
肛門から体内に入れるので規定量の薬の成分を吸収できます。飲み薬や粉薬の場合は赤ちゃんが嫌がって飲まなかったり、上手に飲めなくて吐き出してしまうことがあります。発熱時に嘔吐などが続く場合は飲み薬は難しいですが、座薬だったらどんな状況でもさせるので安心です。
冷蔵保存できる
座薬は約半年はど冷蔵庫で保存できます。赤ちゃんは突然高熱を出すことがあるので常備できると安心ですよね。
座薬のデメリットは?
挿入を嫌がることが多い
座薬を挿入するのが気持ち悪くて嫌がる赤ちゃんは多いです。ママやパパも熱を下げるためとはいえ嫌がるお子さんを無理矢理押さえつけるのはイヤですよね。
腸が荒れることも
座薬は直腸に直接働きかけるのでその分効果が高いのですが、何度もくり返すと腸に負担をかけてしまいます。座薬が処方されたときの回数や時間間隔を必ず守るようにしましょう。
座薬を使う目安は?
・38.5度以上の高熱がでているとき
・熱のせいで元気がなく不機嫌で水分がとれないとき
・熱が高くて寝られないとき赤ちゃんは平熱が37.5度くらいです。小さい子供も大人に比べて体温が高いので37度台でもそれほどつらくないときが多いです。
38.5度未満でも元気がなくぐったりしているときがあります。これは熱が上がっていく段階が一番体がつらいため、元気がないことが多いんです。
熱の高くないときや平熱のときに座薬を使用してしまうと体温が下がりすぎてしまい危険です。高熱がでたときに熱をさげるために使うようにしましょう。
熱が出るのは、赤ちゃんや子供の体内にウイルスや細菌が侵入し体がそれらと戦っているためです。
体の熱を上げることでウイルスや細菌を死滅させようとしています。熱がでるというのは決して悪いことではないんですね。熱によってウイルスや細菌が完全に死滅すれば回復に向かっていきます。
ですので、座薬で一時的に熱を下げるとそのときは体が楽になりますが、使用するタイミングを間違えると座薬の効果が切れたときにまた熱が上がってしまうことがあります。
もし、以下のような状態の場合はなるべく座薬をつかわないことをおすすめします。
・食欲がある
・元気
・機嫌がいい
高熱がでるとすぐに熱を下げた方がいいと思ってしまいますが、まずは赤ちゃんの状態や機嫌をよくみて正しいタイミングで使用するようにしましょう。
座薬をさすタイミングは?
ポイント
座薬は使用するタイミングが大切です。
発熱には3つのステージがあります。
- 熱が上がる
- 熱が上がりきる
- 熱が下がり始める
「熱がピークになったタイミング」で使いましょう。
座薬は熱がピークになったタイミングで使うのが正しいです。人間が熱を出すときは3つのステージがあります。
熱が上がる
体にウイルスが入ったりすることが原因で体温が上がります。熱が上がっていくこの段階が体は一番つらいです。
ですので、赤ちゃんや子供はぐったりしたり、不機嫌になったり、吐いたり、元気がなくなったり、手足が冷たくなったりします。
これらの症状は熱が上がっている段階に起こることがほとんどで、熱と関係なく続くときは熱によるものではなく病気の症状だと考えれます。
この段階では熱が上がっている途中なので座薬は使うのはおすすめしません。寒気や悪寒を感じることが多いので冷やすよりも暖かくしてあげることがよいでしょう。
熱が上がりきる
熱が上がりきると、寒気がとれてきたり、不機嫌や吐き気なども落ち着いてきます。熱があるのに元気になってしまうこともあります。
元気な場合は解熱剤や座薬を使わずに少し様子を見てあげるとよいでしょう。ただし、水分補給を忘れずにしてあげてください。熱が上がりきったら冷却シートや氷枕などで冷やしてあげるとよいでしょう。
夏の暑い日などはクーラーをかけてあげると体力の消耗を防ぐことができます。熱が上がりきったこの段階で38.5度以上のときは解熱剤や座薬を使ってあげましょう。
熱が下がり始める
熱が上がりきった後に熱が下がり始めるとき、解熱剤や座薬によって回復に向かう時は汗をかき始めます。
汗とともに体温が下がっていきます。服を着込んだり布団をたくさんかけたりして外側から温めて汗をかかせようとするのはNGです!
それによって赤ちゃんや子供は不機嫌になったり夏場は熱中症になる危険があります。体の内側から汗をかく必要があるのでお茶やイオン飲料などでこまめに水分補給をして汗をかきましょう。
脱水症状にならないように注意して水分をとってくださいね。
まだ熱が上がりきっていないタイミングで使ってしまうと座薬の効果が切れたときに、また熱が上がり始めてしまうことがあります。熱があがるときの症状がある場合は少し様子を見ることをおすすめします。
座薬をさすときの注意点
ポイント
座薬を使用するときは次の点に注意しましょう。
- 手足が冷たかったらささない
- 使った時間を覚えておく
- 座薬は冷蔵庫で保管しておく
- 子供の体重を覚えておく
- 病院で処方されてたものを使う
赤ちゃんの体重に合わせて座薬を切るときは清潔なハサミや刃物を使い、切り口が斜めになるようにしましょう。
座薬は冷蔵庫からだすと柔らかくなって切りにくくなるので冷蔵庫からだしたらすぐにカットしましょう。
座薬をあまり使ったことがないママも多いかもしれません。座薬を使用するときや保存には注意点があります。次の点を守って使用するようにしましょう。
手足が冷たかったらささない
手足が冷たいうちはまだ熱が上がりきっていません。これからさらに熱が上がることが考えられるのでもう少し様子を見ておきましょう。
使った時間を覚えておく
座薬を使うのは6時間以上あけておくように指示されます。なかなか熱が下がらないとすぐにまた座薬をさしたくなってしまいますが必ず6時間以上あけましょう。また、座薬の使用回数は1日2回までです。
座薬は冷蔵庫で保管しておく
座薬は必ず冷蔵庫で保管しておきましょう。暖かい場所では溶けてしまうためいざ使おうと思ったときに溶けてしまっている可能性があります。必要なときに使えるように正しく保管しましょう。
子供の体重を覚えておく
体重によって使用量が決まっています。薬局で処方される際に4分の3くらいにきって使ってくださいなど指示がありますので必ず守るようにしましょう。体重1kgあたり10〜15mgが目安です。
座薬の切り方
座薬を切って使用するように指示されたときは、清潔な刃のハサミや包丁で切ります。刃が乾燥しているものを使いましょう。手ではキレイにちぎれないので必ず刃物で切るようにしましょう。
キレイに切るために、ハサミや包丁の刃をお湯などで温めておくのがおすすめです!座薬は冷蔵庫から出した直後に切るようにしましょう。冷蔵庫から出して外においておくとどんどんやわらなくなるので切るときは気をつけましょう。
座薬を切るときは、切り口が斜めになるように切るとよいでしょう。座薬は先端が細くなっているので斜めに切ることで分量が調節できます。
病院で処方されたものを使う
座薬に含まれている解熱剤には種類があり、赤ちゃんや子供が安全に使えるのは「アセトアミノフェン」という成分のみでできています。
大人用の座薬や自分で薬局で購入してきたものはアセトアミノフェン以外の成分が含まれているため使用は控えた方がよいでしょう。
特にアスピリンは副作用の危険があるので赤ちゃんには使用してはいけません。必ず小児科など病院で子供用に処方されたものを使うようにしましょう。
座薬の挿入の仕方は?
ポイント
座薬の挿入の手順
- 手を洗って清潔にしておく
- 体の向きを横向きにする
- 座薬を入れやすくする
- しゃべりながら一気に入れる
- 入れたら押さえる
赤ちゃんが嫌がったり、痛がらないように挿入してあげましょう。
また、挿入後はしっかり押さえてあげて赤ちゃんの肛門の中で薬の成分が吸収されるようにしましょう。
赤ちゃんに座薬を挿入するのってドキドキしますよね。熱で苦しがっている赤ちゃんにスムーズに挿入できるように手順を押さえておきましょう!
手を洗って清潔にしておく
入れる前にママの手を洗ってキレイにしておきましょう。赤ちゃんの肛門に雑菌をつけないように気をつけます。肛門付近の皮膚を傷つけてしまうと炎症を起こしやすいので爪をひっかけないように気をつけます。
体の向きを横向きにする
お子さんの体の向きを横向きにしましょう。うちの子は、仰向けでお尻を持ち上げると嫌がってなかなか入れられませんでした!子供にしてみたらお尻を持ち上げられて何が始まるんだろう!?という感じだったかもしれません。横向きにしてあげるとスムーズに挿入できるのでおすすめです。
座薬を入れやすくする
座薬の先端を少し濡らしておくと入れやすくなります!もしくは肛門にオロナインなどの軟膏やベビーオイルを少し塗っておくと滑りがよくなってスムーズに入りますよ。
しゃべりながら一気にいれる
座薬を挿入するときはつい真剣になって黙ってしまいますが、静かになると子供も身構えます!普段通りしゃべりながら入れるのがおすすめ!足を強く持ってしまったり、お尻を高く持ち上げたりするといつもと違う様子を感じて赤ちゃんも嫌がったり寝返りをしたがったりします。今から入れるよというのができるだけ伝わらないようにするっと一気にいれるのがポイントです。座薬を入れるときはティッシュなどで座薬を持っていれると入れた後に押さえるのが楽ですよ。
入れたら押さえる
挿入したら5分くらい押さえておきましょう。座薬は体温で溶けるようになっています。しっかり奥まで入っていないと肛門からでてきてしまったり、外で溶けてしまうことがあります。最低でも5分くらい押さえておくようにしましょうね。座薬を挿入して30分くらいはあまり動かないようにして過ごしましょう。
もし入れた座薬が溶ける前に出てきてしまったらもう一度新しい座薬を挿入しましょう。
ただし、5分以上立ってからでてきた場合は再度挿入はせずしばらく様子を見ましょう。
座薬の解熱効果は座薬を入れてから1~2時間後です。もし、きちんと挿入されたかわからない場合は1〜2時間後に解熱効果が現れているかどうかチェックしてみましょう。
臨機応変に対応しよう
座薬は病気を治したり、体内のウイルスを退治するものではなく一時的に熱を下げるにすぎません。ですので、熱だけではなく赤ちゃんや子供の様子をよく観察しておく必要があります。
熱以外にぐったりしていたり、食欲がない、水分をとらないなどの症状がある場合は早めに受診してください!
熱は怖いものではないので赤ちゃんの様子をよく観察して対応すれば大丈夫ですよ。
できるだけ自然治癒で治したいと思うママもいらっしゃると思いますが、赤ちゃんが苦しそうだったり、つらくて眠れないようなときは解熱剤を使ってあげた方がよく眠れて治りが早くなることもあります。
こだわりすぎず臨機応変に対応するようにするとよいですね。






