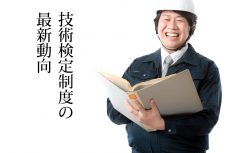国土交通省と東京都の公共工事で拡大「週休2日制工事」と「快適トイレ」
東京都建設局は4月14日、東京都庁第一本庁舎大会議室にて「建設現場の環境改善セミナー~週休2日、快適トイレ~」(後援:国土交通省)を開催した。
同セミナーには東京都や地方公共団体の職員のほか、ゼネコン技術者など約400名が参加し、建設業をとりまく現況や問題点などが周知された。参加できなかった方々のために、講演内容の要点を簡単にまとめておく。
冒頭、主催者を代表して東京都建設局道路監の三浦隆氏が挨拶した後、次の講演が行われた。
- 講演その1「国土交通省における建設現場の環境改善に向けた取組について」
国土交通省大臣官房技術調査課事業評価・保全企画官 桝谷有吾氏 - 講演その2「建設局における建設現場の環境改善に向けた取組について」
東京都建設局総務部技術管理課長 小木曽正隆氏 - 講演その3「建設現場のトイレ改善による社会的波及効果について」
特定非営利活動法人日本トイレ研究所代表理事 加藤篤氏 - 講演その4「週休2日制確保モデル工事を振り返って」
新日本工業株式会社(夢の島公園アーチェリー会場基盤整備工事) 今野真吾氏 - 講演その5「週休2日制確保モデル工事を振り返って」
日鋪建設株式会社(野川河床整備工事その10) 藤嶋延尚氏
今回は、講演その1、2、3、4の内容をお伝えする。
※その5、日鋪建設・藤嶋延尚氏については、別途取材を行ったので、後日紹介する予定です。
国土交通省 桝谷有吾氏の講演「国土交通省における建設現場の環境改善に向けた取組」

国土交通省大臣官房技術調査課事業評価・保全企画官 桝谷有吾氏
今、建設業界の人材不足は危機的な状況を迎えている。建設業の就業者数は、1997年と2016年を比較すると、685万人から492万人へと193万人も減少している。
施工管理技士を含む建設技術者は41万人から31万人に減少し、建設技能労働者は455万人から326万人に減少。さらに建設業界は高齢化率も高く、50歳以上の人材が約30%を超え、29歳以下の若手は10%に過ぎない状況である。
建設業界における人材不足の大きな理由は、他産業と比較して、賃金が少ない点と、週休2日が確保できない点がある。建設業と他産業の出勤日数を比較すると、年間ベースで建設業は251.3出勤だが、全産業は224.4出勤。建設業は全産業と比較して年間約27日も多く出勤していることになる。
そこで国土交通省は建設業の担い手を確保するために、率先して建設現場の環境改善、週休2日の確保に取り組んでいる。
「適切工期の確保」が課題
国土交通省は直轄工事の元請・下請業者の技術者を対象に、週休2日の取り組みに関するアンケートを実施した。その結果、施工管理技士含む技術者や技能労働者の半数以上が完全週休2日または4週8休が望ましいと考えていることがわかった。しかし実際は、国の直轄工事でも4週8休を実施している現場は全体の1割未満。3億円未満工事では、4週4休が最も多く、これに4週5休が続く結果となった。
では、なぜ建設業は週休2日が確保できないのか?週休2日制モデル工事の受注者にアンケート調査をしたところ、施工者からは「適切な工期の確保」を要望する声が多かった。事実、発注者の設計工期と、実働日数を比較すると、もともとの発注者の設計工期が短い傾向を確認した。
これを受け国土交通省は、「週休2日制モデル工事」の「モデル」という表現を削除し、2017年度から「週休2日制工事」と明記する方針を打ち出した。昨年度は165件で「週休2日制モデル工事」を実施したが、2017年度はさらに拡大し「週休2日制工事」を実施する。
そして「週休2日制工事」の拡大にあたり、次の3つの新たな取り組みを2017年度から実施する。
【1】工期設定支援システムの導入
工期設定に際し、歩掛かりごとの標準的な作業日数や作業手順を自動で算出し、根拠を明確に残す工期設定支援システムを2017年度から、原則的に全直轄工事で適用する(維持管理工事を除く)。
【2】工事工程の受発注間の共有をルール化
施工当初の段階から、受発注者間で工事工程のクリティカルパスと関連する未解決課題の対応者と対応時期について共有することを全直轄工事で2017年度からルール化する。
【3】十分な工期の確保
工事の準備と後片付けにかかる標準期間を実態調査に基づき改善する。下半期から試行する。その他の工種についても実態調査に基づき改定予定。
……この3点を強力に推し進めることにより、工期の確保、書類の簡素化などを行い、週休2日を確保できる環境を整備する方針だ。
ぜひ国土交通省の取り組みについて、全国の地方公共団体、民間のゼネコンも自主的に取り組んで欲しい。
◎質疑応答
講演後、質疑応答の場面で、東京都建設局の職員から質問が出た。「建設技能労働者の賃金水準は低く、週休2日制度を導入した場合、日給月給で働く技能者の賃金がさらに下がる問題点があるが、解決策はあるか」という質問だ。
これに対する桝谷企画官の回答は、次の通り。
国土交通省が実施した「週休2日制モデル工事」に関するアンケートでも、約3割の建設技能労働者が給与は「下がった」と回答している。国土交通省としては、週休2日制度を導入してもゼネコンが賃金を下げない努力を望んでいるが、発注者が休日補償するかということについては、まだ議論中である。
ただし、5年連続で設計労務単価を上げている。その上がった分の設計労務単価が建設技能労働者に行き渡っていない現状もあり、まず行き渡らせることが最初の課題である。
今後も関係者と意見交換しながら、週休2日制確保と建設技能労働者の賃金確保は両輪で進めるが、すぐ解決できるアイディアは今のところないのが現状だ。
東京都建設局 小木曽正隆氏の講演「建設局における建設現場の環境改善に向けた取組」
続いては、小木曽正隆東京都建設局総務部技術管理課長の講演「建設局における建設現場の環境改善に向けた取組について」である。
東京都建設局の工事を受注している技術者や他の地方公共団体の技術管理部門にとって参考になる内容だ。

東京都建設局総務部技術管理課長 小木曽正隆氏
「週休2日制確保モデル工事」はこれまで55件実施
東京都建設局は2015年から、建設業に入職しやすい環境づくりや労働環境改善のため、週休2日の確実な実施が重要と判断し、「週休2日制確保モデル工事」をスタートした。
週休2日は、①1週間のうち土曜日・日曜日の休日を確保するパターンと、②1週間のうち、2日間の休日を確保するという2パターンがある。
工事受注者は週休2日の取得計画が確認できる「休日取得計画書」を発注者に提出。その後、受注者は休日取得の実績が確認できる「休日取得実績書」を発注者に提出する。そして工事完了の段階において、アンケート調査等で課題を浮き彫りにし、週休2日が仮に達成できなくても工事成績での減点はしないこととした。
週休2日制確保モデル工事は、近隣住民にも伝えるため、現場の看板に明記。2015年度で5件、2016年度は50件をそれぞれ実施した。
2017年3月末時点で集まっているアンケートによると、週休2日制の区分としては、土曜日・日曜日の休日の確保を選択したケースは24件、2日間の休日確保を選択したケースは5件であった。全体の29件のうち、25件は休日を確保できたが、4件は休日を確保できなかったとの回答があった。休日を確保できた理由として、「モデル工事受注のため」が39%と最も多く、「意識が高かったため」がこれに続いた。逆に週休2日を確保できなかった理由として「工期設定が厳しい」との回答が75%と最も多かった。
また、「週休2日を普及させるために、発注者に求めること」として、「書類の簡素化」が34%と最も多く、提出書類作成が大きな負担になっていることが分かった。書類の簡素化については「受注者提出書類処理基準・同実施細目」の2018年度からの適用に備え、2017年度に見直し検討を行う。
一方、下請け業者から「週休2日の確保に逆行する意見や要望があったか」という問いに対しては、34%が「あった」と回答。その理由として「給料体系も日給月給制が多いため、1日でも多く働きたいのが本音」「雨天中止がある上に、週休2日だと給料が減ってしまう」「土曜日は休日という概念が薄い」「休日は週1日で良い」などの意見が寄せられた。
2017年度の週休2日制確保モデル工事は、上半期契約・債務負担行為の案件では原則実施することから、630件ほどの工事で適用される予定だ。
東京都建設局はWTO案件3件で「女性活躍モデル工事」
東京都財務局および都市整備局は、2016年度から3件の女性活躍モデル工事を実施している。モデル工事は、監理技術者・現場代理人または担当技術者に女性技術者を配置し、配置にあたり、①女性専用の更衣室、水洗トイレ、洗面台、鏡等の設置、および②「女性活躍モデル工事」の広報活動を行っている。
東京都建設局も2017年度から女性活躍モデル工事をスタート。3件あるWTO案件で原則実施し、この3件の工事では、週休2日・女性活躍・快適トイレ・魅力発信のすべてのモデル工事を行うことになる。
東京都建設局は2017年3月以降、施工中の工事から快適トイレの普及促進を開始。3件の実績があり、2017年4月以降は29件で快適トイレの導入を予定している。ただし当初設計では、快適トイレの金額を計上せず、設置できた工事について、設計変更で対応する。
建設産業の職場環境は他産業と比較して周回遅れと呼ばれており、改善をはかりその魅力を発信するときに来ている。将来にわたって社会資本整備や維持管理を安定的に行なっていくためには、担い手の確保・育成が不可欠である。
発注者としても受注者と協力し、積極的に取組むことが重要で、今こそ国土交通省や東京都、民間発注者のさらなる協力が必要であり、建設版”働き方改革”が求められている。
日本トイレ研究所代表理事 加藤篤氏の講演「建設現場のトイレ改善による社会的波及効果」
次は、特定非営利活動法人日本トイレ研究所の加藤篤代表理事の講演だ。建設現場のトイレを改善することは、社会全体に大きなインパクトを及ぼすという。

特定非営利活動法人日本トイレ研究所代表理事 加藤篤氏
国土交通省と特定非営利活動法人日本トイレ研究所は2015年7月、快適な建設現場実現と良質な仮設トイレの普及を目指し、「建設現場からどこでもトイレプロジェクト~仮設から移動式へ」をスタートした。同年8月、国土交通省は建設現場に設置する「快適トイレ」の標準仕様を決定し、翌2016年9月には「快適トイレ」の事例集を発表した。
この「建設現場からどこでもトイレプロジェクト~仮設から移動式へ」は、仮設トイレを快適トイレに移行させるプロジェクトである。トイレ環境の改善を通して、建設現場を地域にひらき、地域に貢献する建設現場を実現することを目指す。
トイレが汚れていれば、その現場全体の志気が高まっていない、道具が乱雑である、安全性に問題がある、など課題を抱えている現場であることが多い。トイレは、担い手確保のための現場の環境改善の象徴的な取り組みである。
快適トイレの波及効果
建設現場のトイレが変わる一次的な効果としては、現場の職場環境が快適になることだが、これをきっかけにイベント、災害時、街中のトイレが大きく変わるという社会的波及効果が大きいと考えられる。
特に災害時のトイレは重要である。熊本地震の被害を踏まえた学校施設の整備に関する検討会資料によると、「備えられなかったために困った機能アンケート結果」では、体育館内の多目的トイレが15%でトップであった。トイレに行けないとなると、飲食を自粛し、身体を壊してしまう。熊本地震では224人の方々が亡くなっているが、「災害の負傷の悪化または避難生活等における身体的負担による死亡者」は169人にも及ぶ。もしトイレが快適であれば、避けられた死もあったはずだ。
快適トイレを増やすことで地域の防災力も高まる。建設現場だけでなく、東京オリンピック・パラリンピック、マラソン大会、花火大会、お祭りのトレイが快適になれば、いざという時に避難所でのトイレに活用できる。
今後、快適トイレの普及推進に向けて、快適トイレの調達一覧(仮称)の作成、快適トイレの認証マーク(仮称)、快適トイレの導入事例の収集、情報共有及び情報発信の場の創出を行なっていきたいと考えており、国土交通省、地方公共団体、民間工事の現場で快適トイレ導入のスピードをより速めていくことが求められている。
新日本工業株式会社 今野真吾氏の講演「週休2日制確保モデル工事を振り返って」
新日本工業株式会社の今野真吾氏は、「夢の島公園アーチェリー会場基盤整備工事」で実際に行った「週休2日制確保モデル工事」を振り返って講演を行った。

新日本工業株式会社(夢の島公園アーチェリー会場基盤整備工事) 今野真吾氏
週休2日の取得日数は111.3%
夢の島公園アーチェリー会場基盤整備工事は、アーチェリー会場整備のうち、新設の予選会場整備のために、既存の多目的コロシアムを盛土し工作作業を設置する事業だった。同現場では、1週間のうち土曜日・日曜日の休日を確保。取得すべき休日日数は62日だったのに対し、実際に取得できた休日日数は69日で、取得率は100%を上回る111.3%であった。
同現場は、園路を運搬路として利用していたため、休日になると子ども連れの家族やマラソン大会、バーベキュー会場の利用者が多く、週末の運搬は危険であると感じていた。そのこともあり、休日確保に前向きな現場運営ができたと実感している。
週休2日取得プロセスとしては、クリティカル工種の工程短縮や、並行作業による工期短縮を目指し、全体工程表を作成した。協力会社と週休2日に伴う作業員・機械代保障料の協議を行い、休日計画表の作成を依頼した。
その後、協力会社の業者を決定し、月間工程表を作成。各業者の毎月の休日計画表を作成し、毎月、東京都建設局に休日取得計画表及び休日実施表をそれぞれ提出した。
並行作業による工期短縮としては、職員の配置をフレキシブルにし、職員の増員を図った。計画時から業者間の調整を行ない、工程に遅延がある場合にフォローアップ会議を実施。毎月、月間工程表を業者に送付し、休日計画表の作成・提出を依頼。各社の計画表をとりまとめ、東京都建設局に提出した。
全工期の計画では、工程や人員配置にズレが生じるため、月ごとの提出を東京都建設局と協議。月ごとの計画を立案したことで、より詳細な検討・計画・実施・考察を可能にした。
新日本工業は積極的に休日取得に取組む
現在、新日本工業の取組としても、月ごとに各現場の休日予定を作成し、実施を記入している。休日取得率を算出し、取得できていない現場・所長にはフォローアップと教育を行っている。
問題点としては、「下請け業者に浸透していない」「日給月給制の作業員は収入が減少する」などが挙げられる。新日本工業としても、今後、率先して休日を確保する体制を構築し、協力会社へモデル現場以外でも休日取得の指導・協力を行うほか、作業員の給与保証などの相談を受ける体制を整える。
今後の現場では、周囲の環境に左右されず休日を確保し、働きやすい建設現場をつくり、若い世代の離職や建設業のイメージの改善に貢献したい。
建設業界は、休みが少ないなどを理由に離職する人も多い。週休2日を確保できる現場をより多く増やすことが求められるが、その一方で工期設定などの課題も多く、さらなる努力が求められる。
建設人材の大量離職時代を10年後に控えている現在、建設業の担い手確保に残された時間はあまりない。国土交通省の桝谷有吾氏の想いを地方公共団体やゼネコンがどのように汲み取っていくのか注目していきたい。