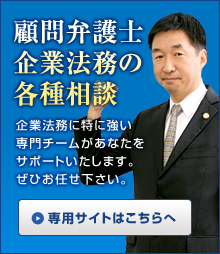契約社員を雇用しているすべての企業で、平成30年春までに、「契約社員の無期転換ルール」への対応が必要です。
「契約社員の無期転換ルール」は、雇用期間が5年を超える契約社員については希望があれば、期間限定なしの雇用契約への転換を強制されるという新しいルールです。
なにも対策をしないと、以下のような問題が生じます。
・問題のある契約社員との雇用契約も、5年経てば強制的に無期限の雇用契約に変更される。
・嘱託社員との雇用契約も、5年経てば強制的に無期限の雇用契約に変更される。
・無期限の雇用契約に転換した契約社員については定年がなくなる。
・無期転換した契約社員の労働条件と正社員の労働条件に不均衡が生じる。
今回の記事では、無期転換ルールへの具体的な対策の方法を、自社でもできるように、わかりやすく解説しています。
必ず確認し、対策を講じておきましょう。
今回の記事で書かれている要点(目次)
- 1,この記事を読めばわかること
- 2,契約社員の無期転換ルールとは?
- 3,契約社員の無期転換ルール対応のポイント
- 4,ポイント1: 基本方針を決める。
- 5,ポイント2: 全員無期転換方針の場合には就業規則の変更が必要
- 6,ポイント3: 転換回避方針の場合には雇用契約書の整備が必要
- 7,ポイント4: 選択的転換方針の場合は選択の時期に注意が必要
- 8,まとめ
- 9,咲くやこの花法律事務所なら「無期転換ルールへの対応について、こんなサポートができます!」
- 10,労務管理に強い「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へのお問い合わせ
- 11,就業規則のお役立ち情報も配信中!無料のメルマガ登録はこちら
- 12,就業規則に関連するその他のお役立ち情報
1,この記事を読めばわかること
●契約社員の無期転換ルールとは?
●契約社員の無期転換ルール対応の4つのポイント
●ポイント1:基本方針を決める。
●ポイント2:全員無期転換方針の場合には就業規則の変更が必要。
●ポイント3:転換回避方針の場合には雇用契約書の変更が必要。
●ポイント4:選択的無期転換方針の場合は選択の時期に注意が必要。
●咲くやこの花法律事務所なら「無期転換ルールへの対応について、こんなサポートができます!」
●就業規則の作成やリーガルチェックに強い「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へのお問い合わせ
●就業規則についてのお役立ち情報も配信中!無料メルマガ登録について
2,契約社員の無期転換ルールとは?
契約社員の無期転換ルールと就業規則の変更の対策についてご説明する前に、まず、「契約社員の無期転換ルールとはなにか」、「対策をしなければ生じる問題点は何か」、「いつまでに対策が必要か」の3点を確認しておきましょう。
(1)契約社員の無期転換ルールとはなにか
まず、契約社員とは、1年契約、2年契約などというように、期間限定で雇用されている従業員をいいます。正社員のように定年までの雇用ではなく、期間限定の雇用であることが特徴です。
そして、「契約社員の無期転換ルール」とは、以下の通りです。
▶「契約社員の無期転換ルール」とは?
契約社員として期間限定の雇用契約を締結していても、雇用契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合は、契約社員から希望があれば、企業はその契約社員との雇用契約を期間限定なしの雇用契約に転換することを強制されるというルールをいいます。
このルールは、平成24年8月に「労働契約法」という法律で定められました。雇用契約が通算で5年を超える契約社員について、期間限定なしの雇用契約への転換を申し込む権利をあたえたものであり、この権利は、「無期転換権」と呼ばれています。
(2)対策をしなければ生じる問題点は何か
仮に契約社員の無期転換ルールについて企業が何も対策しなければ、どのような問題点が生じるのでしょうか?
これについては、主に以下の4つの問題点が生じます。
問題点1:
問題のある契約社員からの無期転換も強制される。
企業は雇用期間が5年を超えた契約社員から、無期転換の希望があれば、応じる義務を負います。そのため、能力や協調性の点で問題のある契約社員についても、雇用期間が5年を超えれば無期転換を強制されることになります。
問題点2:
定年後に再雇用した嘱託社員についても無期転換を強制される。
定年後に従業員を嘱託社員として再雇用する制度を導入している会社では、嘱託社員を1年契約などの有期雇用にしているケースも多いと思います。
この場合は嘱託社員も法律上は「契約社員」に該当し、無期転換ルールが適用されます。
その結果、例えば定年後再雇用した65歳の嘱託社員に無期転換権を行使されれば、65歳から無期限の雇用契約が成立することになります。
問題点3:
無期転換した契約社員については定年がなくなる。
契約社員が無期転換した後は、特に対策をしなければ、契約社員のときと同じ労働条件で無期限の雇用契約が成立します。そのため、無期転換した契約社員については、定年がなくなってしまいます。
問題点4:
もともと転勤がない契約社員については、無期転換後も「転勤なし」になり、正社員との不均衡が発生する。
前述のとおり、契約社員が無期転換した後は、特に対策をしなければ、契約社員のときの同じ労働条件で無期限の雇用契約が成立します。
例えば、正社員については転勤があるが契約社員については転勤がないという会社の場合、契約社員が無期転換した場合には契約社員のときと同じ転勤がないままの条件で雇用契約が成立します。
その結果、「雇用契約は無期だが転勤はない」という雇用契約になり、転勤がある正社員との不均衡が発生します。
このように、契約社員の無期転換ルールについて企業が何も対策しなければ、主に上記4つの問題が生じます。
(3)いつまでに対策が必要か
では、無期転換ルールへの対策はいつまでに必要なのでしょうか?
これについては、多くの企業で採用されている1年契約の契約社員制度の場合、「平成30年春までの対策が必須」になります。
無期転換ルールは、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約からカウントして雇用期間が通算で5年を超えた場合に適用されます。
そのため、契約社員の雇用契約を1年契約で更新を続けている場合、平成25年4月に契約更新した契約社員については、平成30年4月には平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約の雇用期間が通算で5年になり、無期転換権が発生します。
契約社員の無期転換ルールへの対応は、遅くとも「平成30年3月まで」に行う必要があります。
以上、「契約社員の無期転換ルールとはなにか」、「対策をしなければ生じる問題点」、「多くの企業で平成30年3月までに対策が必要となること」の3点をおさえておきましょう。
3,契約社員の無期転換ルール対応のポイント
それでは、以下で具体的に「契約社員の無期転換ルール対応のポイント」をご説明していきたいと思います。
契約社員の無期転換ルール対応のポイントとしておさえておきたいのは、以下の4つです。
契約社員の無期転換ルール対応の4つのポイント
ポイント1:
基本方針を決める。
ポイント2:
全員無期転換方針の場合には就業規則の変更が必要。
ポイント3:
転換回避方針の場合には雇用契約書の変更が必要。
ポイント4:
選択的無期転換方針の場合は選択の時期に注意が必要。
以下で順番に見ていきましょう。
4,ポイント1:
基本方針を決める。
無期転換ルール対応のポイントの1つ目として、まず、「無期転換ルールに対する自社の対応の基本方針を決めること」が必要です。
具体的には以下のいずれの方針をとるか決める必要があります。
無期転換ルール対応について企業がとりうる基本方針の選択肢3つ
(1)全員無期転換方針
(2)転換回避方針
(3)選択的無期転換方針
以下で順番にそれぞれの方針の内容や、メリット、デメリットについて見ていきましょう。
(1)全員無期転換方針を採用する場合について
雇用期間が通算5年を超える契約社員について希望者全員の無期転換に応じるケースです。
5年を超えて雇用契約を更新している契約社員は十分会社になじみ、会社の貴重な人材となっているケースも多いと思います。そうであれば、人手不足の昨今の状況も考えると、全員無期転換するという方針をとる企業は多いと思われます。
この全員無期転換方針のメリットとデメリットは以下の通りです。
●メリット
無期転換を希望する契約社員が全員無期転換することを認めることで、安心して働ける職場にすることができ、契約社員の離職者を減らして、従業員数を確保することができる点がメリットです。
●デメリット
契約社員の多くが無期転換することで、従業員の中の契約社員の占める割合が徐々に減っていきます。そのため、契約社員の雇用調整機能(事業低迷時に契約社員を雇い止めすることにより人件費を減らして企業を維持することができるという機能)が失われる点がデメリットです。
また、問題のある契約社員も含めて、希望者全員が無期限の雇用契約になることもデメリットとしてあげられます。
(2)転換回避方針について
この方針は、契約社員に無期転換権が発生する前に雇止めすることで、契約社員からの無期転換を避ける方針です。
平成25年4月1日以後に開始する有期雇用契約からカウントして雇用期間が通算で5年を超えると、無期転換権が発生しますので、その前の契約更新のタイミングで契約社員を雇い止めし、やめさせてしまうということになります。
この方針のメリットとデメリットは以下の通りです。
●メリット
契約社員を無期転換しないことにより、企業内の契約社員の比率を維持することができ、契約社員の雇用調整機能(事業低迷時に契約社員を雇い止めすることにより人件費を減らして企業を維持することができるという機能)を維持することができます。
●デメリット
すべての契約社員について5年を超える前に雇止めすることになり、有能な契約社員も離職させてしまうことになります
(3)選択的無期転換方針
この方針は、「無期転換する契約社員」と、「無期転換の前に雇い止めする契約社員」を一定の基準で選別するケースです。
この方針のメリット、デメリットは以下の通りです。
●メリット
有能な契約社員についてのみ、無期転換を認めることができます。
●デメリット
契約社員の選別が必要になり、選別の基準づくりが必要になります。また、契約社員を無期転換する人としない人にわけることになり、会社の一体性を阻害することが考えられます。
以上のメリット、デメリットを踏まえて、無期転換ルールに対する自社の対応の基本方針を決めることがまず最初に必要なポイントです。
5,ポイント2:
全員無期転換方針の場合には就業規則の変更が必要
では、続いて、それぞれの方針を採用した場合にどのような対応が必要になるかを見ていきましょう。
まず、全員無期転換方針を採用した場合は、「就業規則の変更」が必要になります。
変更となる箇所は現在の就業規則の内容によっても異なりますが、共通して必要なポイントは以下の点です。
全員無期転換方針の場合に必要となる就業規則の整備の主なポイント
(1)無期転換社員に適用される就業規則を明確にすることが必要
(2)就業規則の転勤条項の確認が必要
(3)就業規則の定年に関する規定の整備が必要
以下で順番に内容を確認していきましょう。
(1)無期転換社員に適用される就業規則を明確にすることが必要
まず、無期転換社員(契約社員から無期転換された従業員)にどの就業規則を適用するかを明確にする必要があります。
これについては、フルタイムの契約社員から無期転換された従業員(フルタイムの無期転換社員)とパートタイムの契約社員から無期転換された従業員(パートタイムの無期転換社員)にわけてご説明します。
1,フルタイムの契約社員から無期転換された従業員(フルタイムの無期転換社員)について
フルタイムの無期転換社員については、「正社員就業規則を適用する」か、あるいは「無期転換社員用に独自の就業規則を作成する」という2つの選択肢が考えられます。
ア:正社員就業規則を適用する場合
フルタイムの契約社員から無期転換された従業員に対して、自動的に正社員就業規則が適用されるわけではありません。
そのため、無期転換社員について正社員就業規則を適用することにする場合は、正社員就業規則の中に、無期転換社員についても正社員就業規則が適用されることを明記することが必要です。
イ:無期転換社員用に独自の就業規則を作成する場合
正社員就業規則の中に、賞与や退職金の制度が設けられており、無期転換社員には賞与や退職金の支払いを予定していない場合は、無期転換社員に正社員就業規則を適用することができません。
このような場合は、無期転換社員についてあらたに独自の就業規則を作ることが必要です。
2,パートタイムの契約社員から無期転換された従業員(パートタイムの無期転換社員)について
パートタイムの契約社員から無期転換された従業員については、無期転換後もパートタイムでの勤務になることが通常でしょう。
その場合、「パート社員用就業規則を適用する」か、あるいは「無期転換社員用に独自の就業規則を作成する」という2つの選択肢が考えられます。
ア:パート社員用就業規則を適用する場合
パート社員には、雇用期間の限定がある有期のパート社員と、雇用期間の限定がない無期のパート社員があります。
そして、雇用契約の限定がない無期のパート社員に適用されるパート社員用就業規則がある会社においては、無期転換社員についてもパート社員用就業規則を適用することが選択肢の1つとなります。
ただし、パートタイムの契約社員から無期転換された従業員に対して、自動的にパート社員用就業規則が適用されるわけではありません。
そのため、パート社員用就業規則に、パートタイムの契約社員から無期転換された従業員にもパート社員用就業規則を適用することを明記することが必要です。
イ:無期転換社員用に独自の就業規則を作成する場合
パート社員用就業規則がない会社や、パート社員用就業規則があっても雇用期間の限定のある有期のパート社員を想定した規則になっている会社では、無期転換社員についてパート社員用就業規則を適用することができません。
その場合は、無期転換社員のための独自の就業規則を作ることが必要です。
(2)就業規則の転勤条項の確認が必要
契約社員については転勤がなかったが、無期転換後は正社員と同様に転勤に応じてもらいたいという場合もあると思います。
その場合は、無期転換社員に適用されることとなる就業規則に「転勤には応じなければならない」という条項が入っているかを確認しておく必要があります。
(3)就業規則の定年に関する規定の整備が必要
高齢の無期転換社員の中には、無期転換された時点で、企業で定めている定年をすでに超えているというケースも考えられます。
そこで、このようなケースも想定して、「60歳を超えて無期転換した無期転換社員については、65歳を定年とする」などというように、無期転換社員の定年を、無期転換社員に適用される就業規則に明記しておく必要があります。
以上、無期転換の希望があった契約社員全員について無期転換に応じる方針を採用する場合は、このような就業規則の整備が必須になります。
例えば、フルタイムの契約社員から無期転換された従業員(フルタイムの無期転換社員)について正社員就業規則を適用する場合の、就業規則の変更例(規定例)としては、以下の内容を参考にしてください。
フルタイムの無期転換社員について正社員就業規則を適用する場合の就業規則の変更例
第●条(契約社員の無期転換)
1 複数回の有期労働契約(平成25年4月以降の有期雇用契約に限る)の通算の契約期間が 5年を超える従業員が、期間の定めのない労働契約の締結を希望したときは、会社はこれ を承諾し、現に締結している有期雇用契約の期間満了日の翌日から当該従業員に本規則を適用する。
2 満60歳以上の従業員が、前項の適用により、会社と期間の定めのない労働契約を締結したときは、当該従業員の定年は満65歳に達する月の翌月の末日とする。
上記の例のように、就業規則の変更、改訂が必要になりますので、平成30年春までに必ず対応しておきましょう。
なお、就業規則の変更届の方法については、以下のの記事で解説しておりますのであわせて参照してください。
▶参考:「就業規則の変更届の方法について」はこちらをご覧下さい。
6,ポイント3:
転換回避方針の場合には雇用契約書の整備が必要
次に、契約社員全員について無期転換に応じない方針(転換回避方針)を採用する場合は、「雇用契約書の整備」が必要になります。
具体的には、契約社員との雇用契約書を締結する際に、「通算で5年を超えて雇用契約を更新しないこと」を明記することが必要です。
これは、契約社員について、5年を超えて繰り返し更新すると、無期転換権が発生してしまうので、転換回避方針をとる場合、通算の雇用期間が5年を超える前に、契約社員を雇い止めすることが必要になるためです。
具体的な規定例としては、雇用契約書の「契約の更新」の条文に、以下のように記載をします。
転換回避方針の場合の雇用契約書の規定例
第●条(契約の更新)
本契約は甲乙協議の上、更新する場合がある。ただし、更新により、平成25年4月以降に開始する雇用契約による通算の雇用期間が5年を超えることになる場合は、以後の更新は行わない。
更新の可否については、従業員の勤務成績、会社の経営状況、契約期間満了時の業務量により従業員ごとに個別に判断する。
甲乙双方が更新を希望するときは、契約期間満了の1か月前から更新後の労働条件について協議する。
念のため、この内容を盛り込んだ雇用契約書のひな形を以下にアップしておきますので、ご参照ください。
▶参考:転換回避方針の場合の契約社員用雇用契約書のひな形(Word/doc)
このように契約社員用雇用契約書の変更、改訂が必要になりますので、平成30年春までに必ず対応しておきましょう。
なお、契約社員の雇用契約書の作成する際のおさえておくべきポイントの詳細については、以下の記事で詳しくご説明していますので、あわせて参照してください。
▶参考:【雛形あり】契約社員の雇用契約書を作成する際に必ずおさえておきたい5つのルール
7,ポイント4:
選択的転換方針の場合は選択の時期に注意が必要
最後に、無期転換する契約社員と、無期転換の前に雇止めする契約社員を一定の基準で選別する選択的転換方針の場合の注意点をご説明しておきたいと思います。
この場合は、以下の3点をおさえておきましょう。
(1)無期転換する従業員の選別について
無期転換する従業員あるいは無期転換しない従業員の選別は、無期転換権が発生するまでに行う必要があります。
つまり、平成25年4月以降に開始する雇用契約による通算の雇用期間が5年を超えないうちに行う必要があります。
選別の時期が遅れてしまった場合、無期転換権が発生してから、転換しない従業員を選んでも、その従業員から無期転換権を行使されれば無期転換に応じなければなりませんので、注意が必要です。
(2)無期転換する従業員に関しては、就業規則の整備が必要
選択的転換方針を採用する場合、無期転換する従業員に関しては、就業規則の整備が必要です。
就業規則の整備のポイントは「ポイント2:全員無期転換方針の場合には就業規則の変更が必要」でご説明した通りです。
(3)転換しない従業員に関しては、雇用契約書の整備が必要
選択的転換方針を採用する場合、無期転換しない従業員に関しては、雇用契約書の整備が必要です。
雇用契約書の整備のポイントは「ポイント3:転換回避方針の場合には雇用契約書の整備が必要」でご説明した通りです。
以上、有能な契約社員のみ無期転換に応じるケースなど、選択的転換方針を採用する場合のポイントについておさえておきましょう。
8,まとめ
今回は、遅くとも平成30年春までに準備が必要になる契約社員の無期転換ルールへの対応について、以下の4つのポイントをご説明しました。
ポイント1:
基本方針を決める。
ポイント2:
全員無期転換方針の場合には就業規則の変更が必要。
ポイント3:
転換回避方針の場合には雇用契約書の変更が必要。
ポイント4:
選択的無期転換方針の場合は選択の時期に注意が必要。
就業規則の変更には、従業員からの意見聴取などの手続きも必要になり、一定の時間がかかります。手続きに必要な時間も見越して、早めの対応をしておきましょう。
9,咲くやこの花法律事務所なら「無期転換ルールへの対応について、こんなサポートができます!」
最後に、無期転換ルールの対応にお困りの企業様のために、「咲くやこの花法律事務所」においてできるサポートの内容をご説明します。
咲くやこの花法律事務所においてできるサポートの内容は以下の通りです。
(1)無期転換ルールへの対応方法に関するご相談
(2)無期転換ルールへの対応で必要になる就業規則、雇用契約書の整備
以下で順番に見ていきましょう。
(1)無期転換ルールへの対応方法に関するご相談
「咲くやこの花法律事務所」の労務に精通した弁護士が、企業の個別の事情のヒアリングをしたうえで、それを踏まえて、無期転換ルールへの対応の基本方針を立案し、また、それに伴い必要になる就業規則、雇用契約書その他各種規定の変更のポイントをご説明します。
(2)無期転換ルールへの対応で必要になる就業規則、雇用契約書の整備
「咲くやこの花法律事務所」の労務に精通した弁護士が、企業に個別の事情を踏まえて、無期転換ルールへの対応のために必要となる就業規則の変更案の作成、労働基準監督署への変更届の提出をサポートします。
また、雇用契約書その他各種規定の変更が必要な場合も、弁護士が変更案を作成したうえで、実際の運用面のアドバイスをします。
無期転換ルールへの対応を正しく行っておくことは、労務環境の整備事項の中でも重要なポイントになりますので、対応に不安がある方は、ぜひ「咲くやこの花法律事務所」の労務管理に強い弁護士のサポートサービスをご利用ください。労務管理のサービス内容についてや弁護士紹介については、以下よりご覧下さい。
▶参考:「労務管理に強い弁護士のサポートサービスについて」はこちらをご覧下さい。
10,労務管理に強い「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へのお問い合わせ
11,就業規則のお役立ち情報も配信中!無料のメルマガ登録はこちら
12,就業規則に関連するその他のお役立ち情報
今回ご説明してきた「契約社員の無期転換ルールと就業規則の変更の対策」のお話と合わせてチェックしておくべき就業規則に関連するお役立ち情報をご紹介します。
▶弁護士が教える就業規則の作成方法!記載事項・届出・変更届の注意点などを徹底解説!
▶【2017年1月施行】育児介護休業法、雇用機会均等法改正に伴う就業規則改訂の重要ポイント!
記事作成弁護士:西川 暢春
記事作成日:2017年5月16日