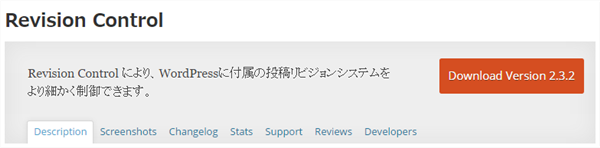ブログ運営の参考に!Naifixで愛用しているWordPressプラグイン31個
『おすすめの WordPress プラグインは何ですか?』
環境によって使うべきプラグインは異なるので、誰でもトラブルなく使えるものを挙げるのはけっこう難しいですが、ご参考までに Naifix で愛用しているプラグインをまとめてご紹介していきたいと思います。
現在の環境に合いそうなものがあれば、ぜひ試してみてください。
目次
絶対に外せない必須プラグイン
WordPress サイトに絶対に欠かせないプラグインは 2 つです。
WordPress初心者におすすめの厳選プラグイン でも解説していますが、どちらも本体インストール時にデフォルトで入っているものですね。
Akismet
WordPress を運営していると大量に押し寄せてくるスパムコメント。これをほぼシャットアウトしてくれるのが Akismet です。現在はコメント欄を開放していませんが、それでもスパムコメントはたくさんきます。
後述する Contact Form 7 と連携すると、スパムメールもある程度ブロックできます。
WP Multibyte Patch
WP Multibyte Patch は日本語 WordPress で必須のプラグインです。
これを入れて動かないプラグインがある場合、そのプラグインに問題があると思われます。
投稿編集作業を補助するプラグイン
Naifix では、管理画面から記事執筆・編集を行うことがほとんどです。ビジュアルモードは使っていません。
デフォルトだとエディタがちょっと使いづらいので、その機能を補強するプラグインをいくつか入れています。
AddQuicktag
AddQuicktag は、よく使う HTML タグやショートコードを登録してボタン一発で呼び出せるプラグインです。
詳しい使い方は以下の記事をご覧ください。
AddQuicktagによく使うタグを登録して記事作成の効率を上げよう
過去記事を投稿順に見直すときは Admin Post Navigation を入れておくと便利です。
投稿編集画面に前後の記事へのボタンが追加されるので、わざわざ投稿一覧に戻らなくても順次編集できます。
Advanced Custom Fields
カスタムフィールドといえば Advanced Custom Fields、というぐらい有名なプラグインですね。
Naifix では、記事下の関連記事を表示するのに使っています。
記事下の関連記事はAdvanced Custom Fieldsで検索・表示するのがおすすめ!
Amazon JS
Amazon JS は、Amazon アソシエイト専用プラグインです。
投稿画面から商品を検索してリンク生成できますが、最近は徐々にカエレバやヨメレバ、Amakuri に乗り換えています。
AmazonアフィリエイトツールAmakuriの使い方とCSSデザインサンプル
Browser Shots
Browser Shots はショートコードでキャプチャ+リンクを生成するプラグインです。
最初は見た目を重視して使っていましたが、テキストリンクだけでもクリック率は変わらなかったので徐々に外しています。
Crayon Syntax Highlighter
サンプルコードの表示は Crayon Syntax Highlighter を使っています。ちょっと重いのが玉に瑕ですね。
詳しい使い方は以下の記事をご覧ください。
Crayon Syntax HighlighterでHTMLやCSSのコードをかっこよく紹介する方法
Duplicate Post
Duplicate Post は、投稿や固定ページの複製が簡単にできるプラグインです。用語集など、フォルムが統一されたページを作成するさいに便利ですね。
Naifix では過去記事を全面的にリライトして新記事として公開するときに使っています。この記事自体も過去記事を再編集したものです ;)
Revision Control
リビジョンはめったに使わないので、Revision Control でリビジョン数を変更しています。投稿の保存数は 2 で、固定ページは保存しない設定です。
Better Delete Revision も併用して定期的にリビジョンを削除していますが、しばらくアップデートされていないのでこちらは使わないほうがよいかもしれません。
WP to Twitter
WP to Twitter は、記事投稿時に Twitter で自動ツイートするために使っています。
過去記事編集時のツイートにはあまり使っておらず、Buffer を使うことが多いです。
Bufferはこんなに便利!Twitter自動投稿をブログ運営に役立てよう
SEO関連のプラグイン
SEO 系プラグインはいくつか使っていますが、入れただけで検索順位がバリバリ上昇するなんてことはありません。基本的に、Google に ブログの情報を素早く正確に伝えるためのもの です。
また、結局はユーザーのことを第一に考えるのが最も効果的です。
Broken Link Checker
Broken Link Checker は、リンク切れを監視してくれるプラグインです。
リンク切れが検索評価を低下させる直接的な要因にならないとはいえ、リンク切れのまま放置しておくのは好ましくありません。きちんと動いていないときは、PHP のバージョンを変更してみてください。
Broken Link CheckerでWordPressのリンク切れをチェックしよう
Google XML Sitemaps
検索エンジンにサイトの構造を伝えるなら、Google XML Sitemaps で XML サイトマップを生成して Search Console から送信しておきましょう。
「送信した URL」と「インデックスされた URL」の差が大きいときは、noindex にしているページが XML サイトマップに含まれている可能性が高いです。noindex にしたページはサイトマップから除外したほうがよいでしょう。
Interlinks Manager
Interlinks Manager は内部リンク構造を把握できる有料プラグインです。
買い切りタイプで使用サイト数に制限がないので、SEO 内部施策を重視しているなら買っておいて損はないかなと思います。
WordPress投稿内の内部リンクをチェックできるInterlinks Manager
PS Auto Sitemap
人が見るサイトマップを作成するなら PS Auto Sitemap が便利です。
メルマガ登録後のサンクスページなど、限定公開しているページがあるなら除外設定しておきましょう。
PubSubHubbub
Google にすばやくインデックスしてもらうことを目的に PubSubHubbub を使っています。
このプラグインを入れておけば絶対に安心というわけではないので、なかなかクローラーが回ってこないときは Search Console から手動で Fetch as Google を実行しておくのがおすすめです。
Table of Contents Plus
Table of Contents Plus は SEO のために入れているわけではありませんが、コード紹介の記事が多いのもあって、このプラグインで目次を自動表示しています。
以下の記事では、具体的な設定方法のほか、検索結果に見出しへのリンクが表示される仕組みについても解説しています。
WordPressに目次を自動挿入するTable of Contents Plusの使い方
Yoast SEO
Yoast SEO は、OGP や meta description の設定、月別アーカイブの noindex などに使用しています。
All in One SEO Pack などもそうですが、SEO プラグインを入れたからといって順位が上がるわけではありません。テーマに同じ機能がある場合は使わないほうがよいです。
WordPressにSEOプラグインを入れただけで順位が上がるのか試してみた結果
軽量化・高速化のためのプラグイン
たまにエックスサーバーに怒られたときだけ WP Fastest Cache を使っていますが、普段はあまり効果が感じられないので外しています。
アクセス数過多でどうしようもなくなったときは、サーバーを見直したほうが早い(速い)ですね。
001 Prime Strategy Translate Accelerator
翻訳ファイルをキャッシュするために 001 Prime Strategy Translate Accelerator を使っていますが、外しても表示速度はそんなに変わらないかもしれません。
キャッシュ系プラグインは設定を誤るとエラーが頻発するので、仕組みがわからないけどとりあえず、というのはあまりおすすめしません。
EWWW Image Optimizer
EWWW Image Optimizer を使うと、JPEG ファイルはプログレッシブに変換されます。
JPEGには2種類ある!プログレッシブとベースラインの違いは何?
ものすごく画像が軽量化されるわけではないので、外部ツールと併用するのがおすすめです。
JPEG軽量化ツール10選-画像圧縮変換後の容量を比較してみた
SNS Count Cache
SNS のシェア数は SNS Count Cache で取得しています。SSL 化をきっかけに、feedly の購読者数もこのプラグインでキャッシュするようにしました。
詳しい使い方は以下の記事をご覧ください。
ツイート数やはてブ数を取得して高速表示できるSNS Count Cacheの使い方
管理系プラグイン
BackWPup – WordPress Backup Plugin
ブログのバックアップは BackWPup で自動化しています。あまり更新していない Naifix ですが、データベース関連は毎日、その他ファイルは毎週というスケジュールです。
どこにどのファイルがあるかよくわかっていない・・・という場合は、一度手動でバックアップしてみるのがおすすめです。
Crazy Bone
Crazy Bone は、管理画面への不正ログインをチェックするために入れています。
攻撃をブロックする機能はないので、セキュリティ強化を図るなら、他のプラグインを使うか Basic 認証を導入しましょう。
Plusin AB Test
Plusin AB Test は、簡易的な A/B テストを素早く実施できるプラグインです。機能が限られているぶん、シンプルなテストを行うのに向いていますね。
詳しい使い方は以下の記事をご覧ください。
クリック率の比較に!WordPressでA/Bテストが超簡単にできるプラグイン
Search Regex
Search Regex はショートコードを外したいときの検索などに使っています。
ブログを HTTPS 化するときも欠かせませんね。
エックスサーバー独自SSLが無料!WordPressサイトをHTTPS化する方法
ブログ運営に欠かせないプラグイン
WordPress をブログとして使う場合に便利なプラグインをご紹介していきます。
Contact Form 7
Contact Form 7 ではなくてもいいですが、お問い合わせフォームは必ず置くべきです。フォームがないだけでビジネスチャンスを逃すことになるかもしれませんよ。
ちょっと見た目も変えてブログの雰囲気に合わせておきましょう。
Contact Form 7のCSSデザインとカスタマイズ方法
Simple GA Ranking
人気記事の表示には WordPress Popular Posts を使うことが多いと思いますが、それよりも数倍軽く、しかも思いどおりに出力できるのが Simple GA Ranking のメリットです。
WordPress や PHP の知識がないと使いこなすのはちょっと難しいですが、テーマをごりごりカスタマイズしているレベルならぜひ使ってみてください。
VA Social Buzz
VA Social Buzz は、誰でも簡単にいいねボタンやシェアボタンを設置できるプラグインです。
有料アドオン VA Social Buzz +SW を入れると、配置の変更や表示パーツの選択など、自分好みにカスタマイズできるようになります。
Facebookの「いいね!」が激増するWordPressプラグインVA Social Buzz
必要に応じて動かすプラグイン
ふだん使わないプラグインは停止するだけではなく削除していますが、必要に応じて再インストールして使っています。
Batch Cat
Batch Cat はカテゴリーを一括して変更するさいに便利なプラグインです。
ただ、最終アップデートが 6 年前ですので、もしかすると WordPress 最新版では動かないかもしれません。かわりによいプラグインがあれば教えてください。
Theme Test Drive
Theme Test Drive を使うと、管理者(または管理者が許可した権限)のみ別テーマを適用することができます。新テーマを使うときの確認などに便利なプラグインです。
WordPressテーマカスタマイズに便利な「Theme Test Drive」の使い方
WP Theme Test という似た機能を持つプラグインもあります。
WordPressのちょっとしたカスタマイズに便利なWP Theme Test
WP CSV Exporter
WP CSV Exporter は、記事一覧を CSV 形式でエクスポートできるプラグインです。カテゴリー整理やブログの分割、キーワードの重複チェックなどに重宝します。
Batch Cat と WP CSV Exporter を使ってカテゴリー整理をする方法を以下の記事で解説しています。
WordPressのカテゴリー見直しと整理に役立つプラグイン2つ+α
まとめ
冒頭でも書いたように、WordPress のプラグインは『おすすめのものを全部入れておけば間違いなし!』ということはありません。
サーバーやテーマ、WordPress のバージョンによっては不具合が出るかもしれませんし、プラグイン同士の干渉も起こりえます。目的に応じて必要なものを探し、勉強しながら使っていきましょう。
一気に複数プラグインをインストールするのではなく、バックアップをとりながら一つずつ試してくださいね。
それでは、また。