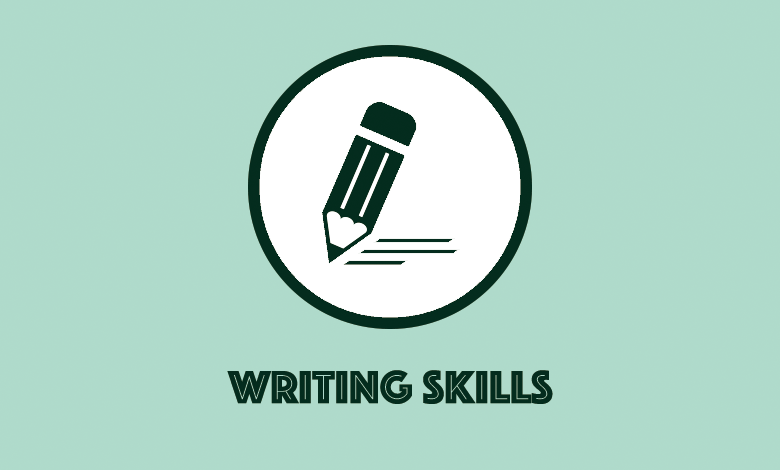
自分の書く記事を多くの人に見てもらって、評価されたい。
そう思って、あなたは文書を書くことに熱心に取り組んでいるのではないだろうか?
しかし、なかなか上手く文章を書くことができず、未だに評価されない、
もしくは評価されるイメージが湧かないといった状態にまで陥ってしまっていないか?
そこで、この記事ではそんな現状を打破するために、
”あなたの書く文章が評価されるようにするためにはどうすれば良いのか”という点について
「文章の本質」を軸にお伝えしていこうと思う。
この本質さえつかむことができれば、
- ブログ
- レポート
- ビジネス文書
- メール・ライン
すべての文章に応用が効き、「いいね!」と認められる文書を
書くことができるようになるだろう。
もちろん、たくさんの人の目にとまる、
拡散される記事を書くことも夢ではない。
評価される文章とは何だろうと悩んでいて、
その答えを知りたいと思う方は、ぜひ読み進めてみてほしい。
「あなたにとってのヒント」を見つけることはできるだろう。
目次
1.評価される文章と評価されない文章の大きな違い
まず、あなたに大切な質問をしよう。
あなたが今、書いている文章というのは、実際のところ何を達成したいのか?
そしてそれをしっかりと達成できているのか?
この質問に対して、あなたは
様々な「意図」を思い浮かべたと思う。
例えば、
- 「伝えたいことがあってそれをブログで発表するため」
- 「文章を書き上げることによって、仕事を達成したいがため」
などである。
文章を書く上で達成できることは大きく2つある。
あなたがどちらに当てはまるのか考えて欲しい。
- 自分の書く文書を通じて、「自己」を満足させることができる。
- 自分の書く文章を通じて、「他者」を満足させることができる。
この2点になる。
そしてこれが評価される文章と評価されない文章の大きな違いになる。
1−1.あなたの文章は他者を満足させる文章になっているか?
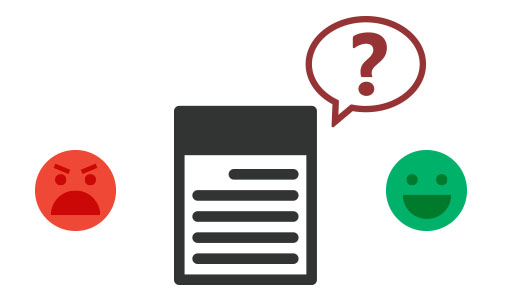
後者が評価される文章になるのは一目瞭然だろうが、
この2つの違いについて解説していこう。
以下の解説を読み進めながら、
あなたの文章はどちらに該当するのか、”客観的”に判断してみてほしい。
まず1つ目の「自己を満足させることができる」というものについてだが、
これは、文章を「自分のために」書いている状態だ。
「いやいや、そんなはずはありません!」
とあなたが思うのはよくわかるが、
恐ろしいことに、たいていの人は無意識下で文章を自分のために書いている。
これは客観的に物事を判断できない、人間の認知的な部分によるものだ。
「自分のための文章」をわかりやすく極端な例で言うと、
”文字数を目安に”レポートを書くことがまさにそれだ。
自分の課題を終わらすことだけを目的に文章を書くと、どうしても評価されることは難しい。
レポートにおいては極端な例だが、
もう少し現実的なところで、あなた自身、自分にこのような問いかけをしてみてほしい。
- 仕事においても、とりあえず言われた通り文章を書ききることが目的になっていないかだろうか?
- ブログ記事が自分の言いたいことだけを言っている独りよがり記事になっていないだろうか?
これらの問いを客観的かつ真剣に考えてみてわかるのは、
あなたは意外にも「何も達成できない文章」を書いてしまっているということだ。
そうすると、「評価される文章」を書くことが不可能になってしまう。
自分で気づかずに、自己満足の文章を書いてしまうのは
よくあることであり、そうなってしまうのもわかる。
しかし高評価を目指していく上で、本当に大切なのは、
2つ目の「他者を満足させる」点にフォーカスできているかどうかなのである。
1−2.他者を満足させる文章とは?
では、他者を満足させる文章とは何なのだろうか?
他者を満足させる文章とは、
「コミュニケーションの設定がなされた上での文章」だ。
文章も、ある意味ではコミュニケーションと同じであり、
読み手がどう反応するか想像し、文章を書いていかなければならない。
それを第一に考えた上で文章を作成していなければ、
結局、自己満足で終わってしまう。
逆に言うと、それさえ押さえれば、多少稚拙な文体であっても
賞賛される文章になるだろう。
これをまず念頭に置いてもらい、本題に入っていくとしよう。
2.「文章の本質」について
「他者を満足させる文章が大事」ということを踏まえれば、
この記事お伝えしたかった文章を改善していく上での本質的な解決策が見えてくる。
2−1.他者を満足させる文章に必要な要素とは
文章を改善していく上での、本質的な解決策は何かというと、
「読み手の視点に立った文章が書かれているかどうかチェックすることだ」
例えば、小学生相手に小難しい言葉を並べたところで、
その文章が大変素晴らしいものであっても、ほとんど通じないだろう。
この場合、小学生にとってわかりやすく文章を書いてあげることが必要になる。
つまり”読み手に合わせたライティング”というのが、
この記事であなたにお伝えしたかった本質の部分だ。
あなたの書く文章は読み手に合わせたライティングになっているだろうか?
読み手に合わせたライティングかどうかを判断するには
文章の冒頭部分がどのように構成されているかどうかで決まる。
2−2.読み手にとって冒頭部分が大切な理由
冒頭部分は、文章全体が読み手にとって良いのか悪いのか判断するのに
最も適している部分だ。
なぜなら冒頭部分は、
読み手が「自分のこと」かどうかを判断する第一段階にあたるからだ。
この第一段階さえ突破すれば、
最後までしっかり読み進めてくれる確率が上がることになり、
最終的にしっかり評価してくれる文章になりうるだろう。
文章はまず「読み進めてくれる」かどうかが大切だ。
特にWEBの文章については、「読まれるまで」が大事だとよく言われているはずだ。
もし内容が素晴らしい文章を作成したとしても、
導入部分が読み手の興味を惹くものでなければ、評価されることは難しい。
読み手の評価基準は「快く読み進めてくれるか、くれないか」いたってシンプルだ。
現状、あなたの記事が評価されていないのであれば、
「冒頭部分の構成」に何か問題点があるということだ。
あなたはいつもどのように文章を書き出しているだろうか?
もし、客観的に自分の文章を評価した時に、
読み手に合わせたライティングが実現できていないのであれば、
ぜひ、ストーリー形式を用いて文章を書き始めてほしい。
ストーリー形式とは、物語調なものを想像されるかと思うが、
ここで定義するストーリーというのは、「読み手目線のストーリー」を意識して書くことを指す。
つまりストーリー形式というのは、
あくまで読み手の中でその文書を読むに至った「きっかけ」を的確に把握し、
それを満たすように誘導してあげることがここで定義するストーリー形式だ。
WEB 上の文章においては、
「なんとなく良さそうだから」と思って文章を読んだ人に対して
「そうそうこれが知りたかったんだ!」と思わせれば勝ちだ。
もちろん何となく読んでくれた人に対しては、
解読を迫らない、わかりやすい構成にする必要があるというわけだ。
3.読み手との大きな壁を壊せるのがストーリー形式
読み手側との大きな障壁がある限り、
あなたの書いた文章は、読み手が必要と感じてくれない限り読み進めてはくれない。
少し、想像してほしい。
読み手は、自分が本当に読みたいベストセラーの小説を読むように
あなたの文章を読んでくれるだろうか?
答えはNOだ。
なぜなら、興味のない文章を読んでいる読み手の頭の中では、
常に関係のないことが頭の中で散乱しており、
無関係の雑念によってあなたの文章を読むことをいつの間にか放棄してしまうからだ。
こうした雑念を振り払って、文章を読み進めることは、
読み手にとって大変な努力を要することになる。
あなたも、本を1〜2P読み進めたが、
実際には1語も頭に残っていなかったという経験をしてはいなかっただろうか。
それは頭の中にある様々な雑念を追い払えていなかったためである。
読み手が喜んで努力を払い読もうとする文章というのは、
「是非そうしたい!!」という願望がある場合だけということだ。
結局のところ、あなたの伝えようとすることに対して、
自然と集中しやすくなる仕掛けを作ることがキーとなる。
それが読み手との壁を壊していく仕掛けになるのだ。
さあ、いよいよここからストーリー形式の具体的にどのようにして使えばいいのかを説明していこう。
4.ストーリー形式の手順
読み手というのは、文章を読むまで、
実は自分の頭の中にある興味を確実なものにできていない。
例えば、「最初は美味しいラーメンを食べたいな」となんとなく探していたのだが、
いろんなラーメンの種類を見て回ることで、本当のところ自分は醤油ラーメンが
1番今食べたいラーメンの種類だったのだとようやく認識できる。
あなたもそういった経験はなかっただろうか?
ストーリー形式を用いることは、
本当の所での読み手の興味関心をはっきり具体的にさせることである。
興味関心を引き出して、
読み手に具体的にステップを踏んでもらうには、
①状況→②複雑化→③疑問
このパターン通りに文章を展開することができれば、
書き手と読み手が同じ場所に立つことができる。
つまり読み手に「読み進めてもらえる状態」になってもらえるのだ。
しかし「状況」や「複雑化」、「疑問」など言われたところで、
抽象的すぎてこれらが何を示しているのかわからないだろう。
そこで、今から1つずつ詳しく紹介していく。
4−1.状況(主題に関して確認されている事実)
「状況」とは、読み手がすでに知っていることや
または知っていると考えて差し支えないことになる。
つまり、読み手が「合意」してくれる内容でなければいけないということだ。
例えば、
「あなたは〜で悩んでいませんか?」
「現状我が社は〜ですよね?(確認)」などである。
これに対して「合意」してくれれば「状況」のステップにおいては成功である。
この読み手に「合意」を得てから読み進めてもらうというのは、
読み手の文章に対するハードルが心理学的に低くなると言われている。
読み手がより親近感を持って読み進めてくれるように、
こちらからも読み手側の状況を説明して、読み手自身が再確認できるようにすることが大切だ。
もし、この記事の書き出しから「ストーリー形式が大切だ」という主張してしまうと、
あなたはどう感じていただろうか?
おそらくあなたは自分自身の置かれた背景を再確認できないまま文章を読み進めてしまっていただろう。
書き出しは、読み手にとって「本当に知りたいこと」なのかどうかを再認識してもらいたい。
だからそこ疑問を抱かせるために「状況」を一番冒頭で説明することは大切だ。
4−2.複雑化(状況の次に起こった疑問へとつながる事柄)
複雑化とは、
状況を受けて進められる思考のプロセスとして疑問の間に存在しているものだということだ。
この記事で言うところの「熱心に文書を書いているが評価されない状態」を指す。
現状に何かしらの不満や、変化があるからこそ
現状が複雑化していくことになる。
「複雑化」がなければ、次のステップに繋がらない。
「疑問」のステップとの橋渡しのために「複雑化」は必須だ。
正確に言えば、書き手が読み手を想像して伝えようとしている物語の中で起こる「複雑化」であり
これが緊張を発生させ、疑問の引き金になる。
4−3.疑問(本題に導く読み手の問い)
疑問については、読み手側の状況から
どのように疑問が浮かんでくるか、リアルに想像していかなければならない。
例えば、状況から何かしらの変化が起き、
「それを対処、解決するためにはどのようにすればいいのか?」
というようなものが「疑問」のステップである。
「疑問」のステップで大事なのは、
読み手を本文に誘い込むことができるかどうかだ。
「続きはCMの後で」と言って、CM明けまで待ってもらえるような、
読み手にとって興味関心のある疑問を提示しなければいけない。
5.具体例:この記事のストーリー形式
少しわかりづらかったかもしれないので、
ここで具体例としてこの記事においてどのようにストーリー形式が使用されているか説明しよう。
この記事自体はどのような構成になっているのかというと
下記のようになっている。
-
自分の書く文章を多くの人に評価されたいと思って熱心に文章を書いている。(状況)
-
しかしなかなか評価されない。評価されるイメージが湧かない。(複雑化)
-
どうすれば文章が評価されるのか?
文章を評価されるために知るべき、文章の本質とは何か?(疑問)→この疑問を本文で明かす
導入部はこうした読み手の思考プロセスに沿ったものであり、
読み手の本来感じていたことを思い起こすものにしなければいけない。
読み手の本来感じていたことを複雑化し、
疑問まで持っていける記事はかなり強い。
なぜならこちらがターゲットしている読み手のことを120%満足させれるからだ。
そのためにこの記事でも、状況→複雑化→疑問のフレームワークを使用している。
5.導入部の長さについて
さて、いざ書き出してみよう構成を練ってみると、最後に疑問が1つ浮かぶ。
導入部の長さはどれくらいが適切なのだろうか?
答えとして、導入部は読み手をあなたの考えに導く前に、
あなたの読み手が「同じ土俵に立っている」ことを確信できるくらいの長さがあれば十分だ。
一般論で言えば、導入部は2つか3つの段落で十分だと言える。
多くて4段落、それ以上長くしないほうが適切だ。
なぜなら、すでに知っていることを思い起こさせるには
だいたい1〜4段落くらいの記述で事足りるからである。
もし、それ以上の段落や図などを用いて説明しているとしたら、
それは間違いなく、くどい説明になってしまっているだろう。
また、読み手との距離が近い場合には、逆に導入部が短く済むこともある。
導入部の長さは、その後に続く本文の長さとは必ず関係があるものでなく、
むしろ、読み手の必要性と関係がある。
導入部の長さというよりも、
あなたの伝えたい主たるポイントの重要性を十分に理解してもらい、
かつ、あなたの伝えようとすることに関心を持たせるために、
読み手に何が必要なのかを考えることが一番大切になる。
6.良い導入部の3つの条件
最後に、これまでを総括して、良い導入部の三つの条件を記しておく、
あなたが文章を書く際、参考にして頂ければと思う。
6−1.読み手のニーズを思い起こせている
よく、「世間の情勢はこうなっている」という書き出しから始まる記事を見るが、
読み手が本当に欲しいのは前提知識ではない。
読み手にとって妥当な内容かどうか、
ニーズをとらえた上でしっかりと説明することが一番大切だ。
6−2.状況・複雑化・解決の三要素を含ませている
常にこの3要素を入れておくというのは必須だが、
順番を変えた方が意図が伝わるのであれば、無理に順番通りにする必要はない。
6−3.テーマに応じた導入部の長さになっている
先ほどの「導入部の長さについて」の説明した通り、
導入部の長さは読み手の理解が得られるのであれば短くても構わないし、長くても構わない。
大切なのは、主題まで誘導できるかどうかだ。
長い文章になるほど、次に何が書かれてあるのかを事前に紹介しておくといいだろう。
7.最後に
結局のところ、「文章」を書いていく上で必要なのは、
読み手の「疑問」を解決することが中心軸になる。
しかしながら「文章」はついつい失敗しがちだ。
なぜなら相手の顔が見えないからである。
相手が何を求めていて、求めていないのか。
何が好きで、何が嫌がるのか。
その反応を伺うことができない状態は、
コミュニケーションにおいて最上級といっていいほど難易度が高い。
そもそも対面のコミュニケーションであっても
うまく相手の顔色を伺うことができず、
自分の思っていることをうまく伝えられないことだってたくさんある。
だがしかし、そこで物怖じせずに頭の中に入れておいて欲しいのが、
あなたの書く文章に興味を持ってくれる読み手は、
一人や二人は存在しているということだ。
その唯一の読み手を意識した文章を作成することを、誰よりも心がけることが何より大事だ。
多くの人を感動させるよりもまず、
1人の人を120%感動させる気概を持ってほしい。
それを忘れずに書き出せば、
あなたの書く文章は必ず評価される文章になっていくだろう。
文章で「誰」に「何」を与えることができるか?
潜在的にすごいパワーを持っている無名のブロガーさんはたくさんいるが、
それを活かしきれていない人があまりに多いと感じている。
文章の評価は「文体」では決まらない。
大切なのは、「誰」に「何」を伝えるか?という点だ。
ブログだと、
- そのキーワードで検索した人を限りなく満足させる記事を書くのか?
- より最新の情報を求めている人のために即時性のある記事を書くのか?
ビジネスだと、
- 上司やクライアントは何を求めているのか?
- ユーザーは何を求めているのか?
この機会に上記の項目をもう一度よく考えてみるといい。
あなたの持っている素晴らしい文章を
「あなただけのため」に使うのはもったいない。
あなたは、もっともっと素晴らしい文章を書ける可能性を秘めている。
”文章の本質”をいち早く掴み、
世の中により良いアウトプットを出して欲しい。
参考・文献考える技術・書く技術バーバラ ミント ダイヤモンド社 1999

コメント