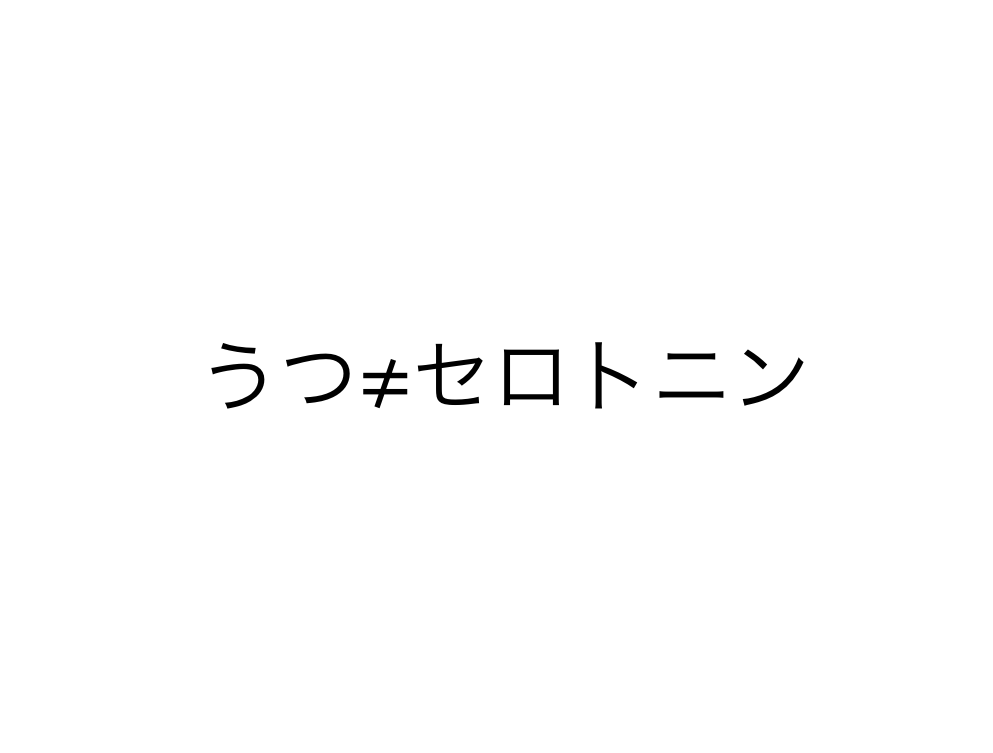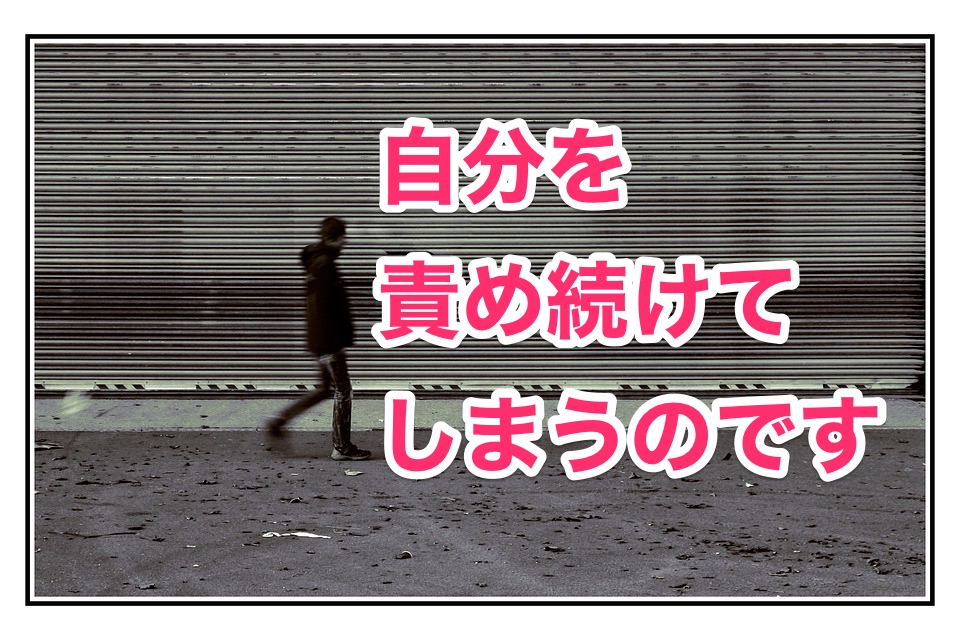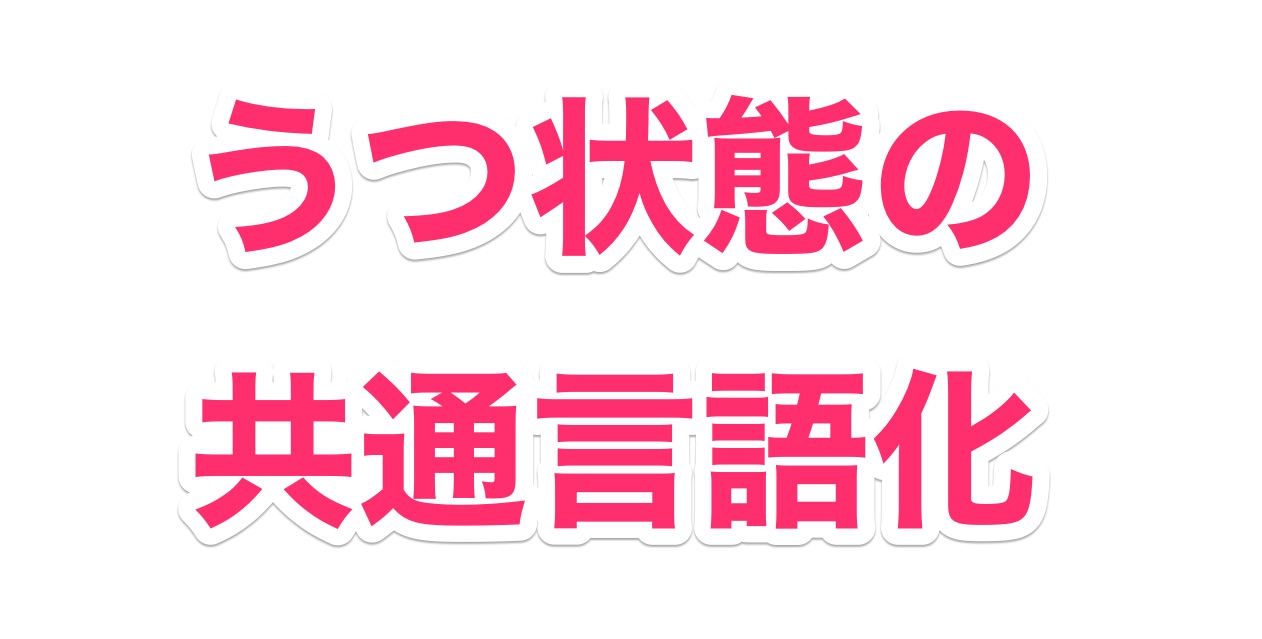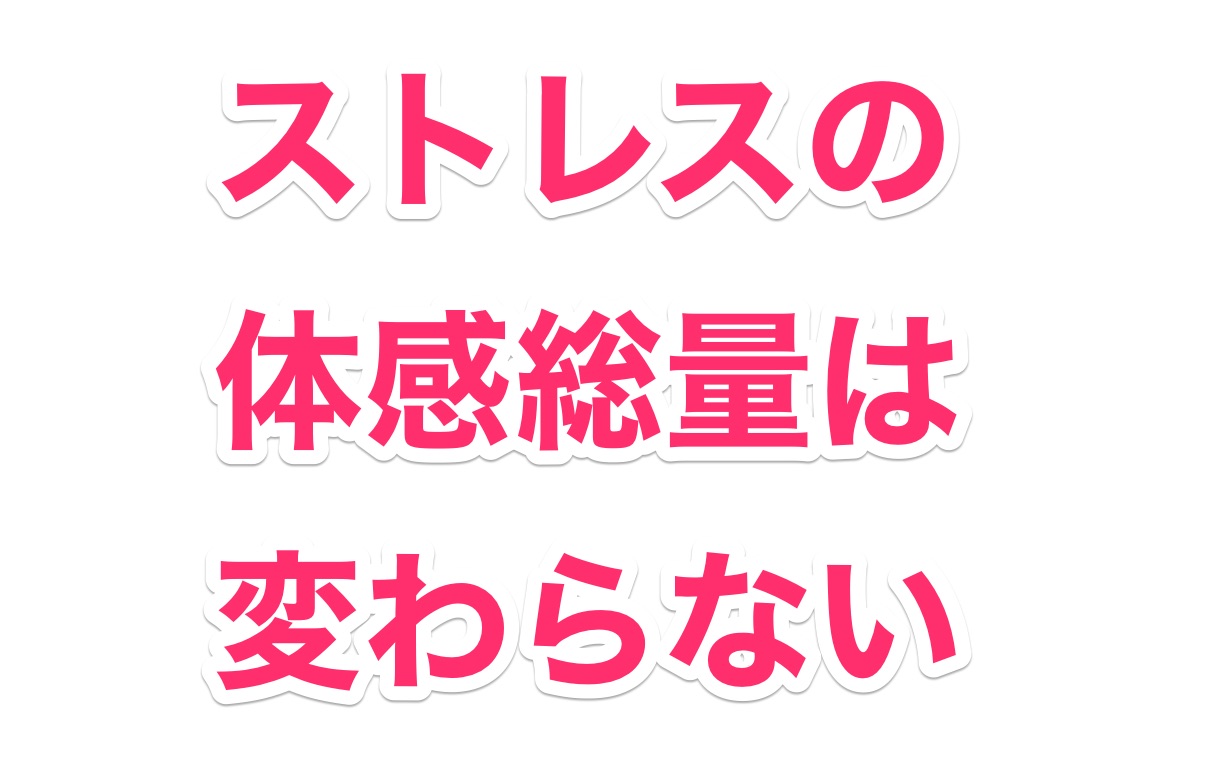どうも、双極性障害と戦うブロガー星野 良輔(@hossy_FE_AP)です。
精神疾患であれば誰でも抗うつ剤をはじめとする精神科薬を飲んでいると思います。
医師からどのように説明されましたか?
私は以下のように説明されました。
おそらくあなたも同じでしょう。
しかし、セロトニンが増えればうつが治るという科学的根拠は何もないようです。
それどころか、関係なかったと証明されちゃってました。
うつ=セロトニン不足は間違っている
うつ病がセロトニンの減少に関係するのではないかという仮説を立てたのは、ジョゼフ・シルドクラウトという人だ。セロトニンやドーパミンが精神病に関係するのではないかという仮説を、モノアミン仮説という。
しかし提唱したこの仮説はすでに否定されている。仮説というより関係ないと「証明されている」のだ。
にもかかわらず、たとえば二〇一〇年に発表された研究によれば、アメリカ人の八七%が統合失調症はセロトニンやドーパミンがバランスを失っているという「化学的不均衡論」が原因であると考え、またうつ病も八〇%の人が同じように考えているという結果が出ている。
この件に関してアメリカ精神医学雑誌「the American Journal of Psychiatry」には、うつ病の化学的不均衡理論を再検討した医師たちによる以下のようなレビュー記事が掲載されている。
「一〇年以上にわたるPET study、モノアミン枯渇に関する研究、およびモノアミン関連遺伝子の多型性を調べる遺伝子関連解析の結果、
うつ病の病態生理において、セロトニン系、ノルアドレナリン性、またはドーパミン作動性神経伝達の実際の欠陥に関係すると思われるエビデンスはほとんど存在しなかった
セロトニン不足=うつ病は誰もが疑いもせずに信じ込んでいることですが、実際には否定された仮説なんだとか。
そう、私は現在、双極性障害の治療薬としてレクサプロを飲んでいます。
レクサプロはSSRIで、セロトニンを増加させる役目があるわけです。
それでうつを改善しようってな算段ですが……うつを治すのにセロトニンが関係ないなんて言い出したら、私の考えは完全に見当違いですよね?
仮説は否定されているし、科学的なエビデンス(証拠)も取れていないとの記載があったわけだし……。
抗うつ剤は「プラセボ効果」が働いている
十三年間にわたる臨床試験データを調べた結果、五六%の研究で、代表的な六種類の抗うつ薬について、服用した場合の改善率が、プラセボ(偽薬)を服用していた場合の改善率と差がないことがわかったというのである。
(中略)
データを解析した結果、改善効果の八〇%は、プラセボ効果による心理的効果であると結論づけている。
引用:うつと気分障害
抗うつ剤についての研究結果で、ポジティブなものはほとんどでてきません。
先ほどのように、セロトニンとうつには全く関係が見られなかったというものであったり、抗うつ剤の効果はの80%がプラセボだと結論付けられたり……。
ここまで抗うつ剤を否定すると、飲まないほうがい良いのではないか?と考えてしまいそうです。
抗うつ剤は飲まない方がいいの?
正直に言うと、飲まないでいいのか?についてはわかりません。
私もおそらく、レクサプロという抗うつ剤を飲んで良くなったのですがそれを証明する手段がないのです。
レクサプロを飲むことで、症状が改善したような気は……しますが、果たしてそれは薬による効果なのか、ただ単にストレスの環境から開放されただけだからなのかはわかりません。
ただ、明らかにレクサプロの副作用だと思われるものはありました。
だからといっていきなり断薬することはオススメできません。
精神医学がペテンだという研究結果は数多くある。精神医学が効果をもたらしているという研究結果は少ない(主観的に診察なので効果がわからない)
また、抗うつ剤はやめた方が治るというのも研究結果が示してある。
ただ経験者としてはいきなりの断薬は推奨できない……うーん😣
— 星野 良輔@双極性ブロガー (@hossy_fe_ap) 2016年9月13日
私も、過去に断薬してしまったら、体の震えとか、不眠症状が出ました…。
かなりキツかったです。
いきなりの断薬は、するものではないと、そのとき感じました。 https://t.co/FTHUeeKFln— マエイ (@maeeeeei) 2016年9月13日
精神科医療を信じ過ぎないようにしよう
科学的根拠があるのは、「薬が効いていない」というデータ。
それが全て正しいとはいえないけど、客観的なデータを示せる方を信用してしまうのも事実です。
抗うつ剤がしっかりと聞いているという客観的なデータと、抗うつ剤は全く効いていないという客観的なデータが示されてはじめてまともに付き合わせることができる。
現時点で、薬が効いている!という主観的なデータと、薬が効いていない!という客観的なデータを並べられた場合、精神科医療はペテンであるという結論に至るのは自然な流れだと思います。
患者として私たちは、今すぐに薬を辞めることは危険です。
ただ、精神科医にすべてを委ねてしまいがちです。自分を守るためにも、精神科医療ではどういったことが語られているのか知る機会は必要だと思います。
精神科医療を全否定することは、病気である自分を否定しなくてはならないので、なかなかつらいところ。
誰しも一人一人に価値はある。それはメンヘラだろうがなんだろうが変わんない。けど、「精神医学の否定」は「メンヘラの存在理由の否定」に繋がる。
— 星野 良輔@双極性ブロガー (@hossy_fe_ap) 2016年9月13日