
何故(自分がいいと思わない)あのバンドが売れて、(自分がいいと思う)このバンドが売れないのか? と疑問に感じたことは一度や二度じゃない。僕は悔しいな、もったいないなと思ったことがたくさんあったけれど、ファンの立場ではどうしたらいいのか全くわからなかった。僕にできることと言えば、友達にCDを貸したり、カラオケで歌ってみたり(でも誰も知らないから場が白けてしまうのであまりできない)、友達をライヴに誘ってみたり(でも押しつけになったら悪いから、あまりできない)、コピーバンドをやってみたり(でもあまり上手くないから逆効果だったかも)と、リスナーの立場でできそうなことは色々やったけど、一人のファンができることって限られていて・・・そんな限界を感じながら悶々とした日々を十数年送ってきた。結構長いよね・・・(笑)。一方で個人的にクエスチョンが浮かぶバンドでも魅せかたや運営がうまいアーティストもたくさんいるのを見ると、音楽の良さ以上に運営がいかに大切であるかを思い知らされる。
また「もったいないな」と思うバンドが世の中にはたくさんいる。何かというと「音楽の届け方」。企業人の端くれとしてマーケティングの仕事に10年以上関わってきた立場からすると、残念だなと感じるバンドが多い。CDリリース時の露出のタイミングや事前の仕掛け、ライヴに出演したときの次のライヴへのつなぎ方、チケットの売り方など気になる点がたくさんある。
近年音楽業界の方と話をすると元気がない人も多い。レコード会社、レーベルの人を筆頭に、ミュージシャンやそれを支えるスタッフもみんな口を揃えて“厳しいし大変だよ”と言う。それは音楽ライターの現場でも同じで、昔は1本の取材で5万円、10万円に取材経費まで出ていたのが、最近は経費込みでインタヴュー1本3万円、予算の少ないWEBメディアでは1万円といった話も聞くようになった。同じライターでもIT系だと3万、5万は当たり前で、医療系では10万円といった話も聞くので、音楽業界全体にお金がまわってきていないことを改めて感じる。
いつからかステージで夢を与える立場の人が、最近はその大変さを自虐ネタにするようになった。以前はほとんどMCをしなかったバンドが、時間をとってグッズやCDの宣伝をめいっぱい行うようになってきた。もちろんビジネスなのだから、宣伝行為は当たり前であるし、スタッフに言われて仕方なくやっているバンドもあるけれど、そうはいってもというのが音楽ビジネスだ。スタッフが宣伝するならともかく、当のミュージシャンが宣伝することに嫌悪感を覚えるファンが少なくないのと、それをかっこ悪いなと思うリスナーやファンもいるからだ。ミュージシャンは芸能人でもあり、夢を売る特殊な仕事でもあるからだろう。
だから数年前にキリンジがライヴでグッズ紹介のためにまとまった時間をとったときは驚きを隠せなかった。僕の周りのファンの間ではあのキリンジまで・・・と話題になったし、今年に入ってクラムボンがメジャーレーベルを離れてDIYでやることを宣言、この春に行われた全国ツアー「clammbon 2016 mini album 会場限定販売ツアー」の各会場で、毎回20分から30分もの時間を使って音楽ビジネスの説明を行い、自分たちが何故レーベルを離れたか、CD1枚からいくら自分たちの手に残るのか、何故CDやグッズを会場で直接販売することにしたのか、その考え方を懇切丁寧にファンに向かって説明している姿を観たとき、時代が変わってきていることを改めて感じた。
僕は音楽業界に興味があったからか、10年近く前からこの種の聞くようになったんだけど、それはあくまで音楽ビジネスに携わっている人、一部の人達だけの話で、リスナーには関係のない話だった。大学時代の友達に話をしても、ちんぷんかんぷんといったところで、音楽や出版ってなんだか大変らしいね、といった程度の認識。だからこそ、それをミュージシャン自らファンに対して解説をする、しかも武道館クラスのアーティストがライヴというファンからお金をいただいている場で貴重な時間を使って行ったことに衝撃を受けた。でもそれを聞いていたファンの多くは前向きに音楽ビジネスの現状や、クラムボンのやりたいことを理解したように見える。終演後に見られた物販の長蛇の列や、先日ミトがツイッターで、今回のツアーでCDが思っていたよりもたくさん売れたとつぶやいていたことがその証だろう。もちろん僕も行列に並んだうちの一人だけど。
少し暗い話題になってしまったが、ここで僕が伝えたいことは、バンドがポジティブな未来を作っていくために必要なことが何かを一緒になって考えたいということ。レコード会社に所属しないと音楽ができなかった時代と、パソコン1台でCDリリースすることができる時代では、自ずとバンドがやるべきことや活動スタイルは異なって当然だから。ここ数年、年齢関係なく元気なインディーズバンドの活動形態を見ると「少数精鋭のチームを作ってバンド運営を行う」ところが多いようだ。
それは常に固定費が発生するような会社的組織ではなく、必要なときに必要な契約を結ぶプロジェクト形式のワーキングスタイル。個々のスタッフが組織に縛られるわけでもなく、仕事に必要な能力を提供しあって一緒にやっていくスタイルである。意識としてはプロボノに近い。
バンド運営には色んな仕事がある。ざっと書き出しても、レコーディングやマスタリングのエンジニア、マネージャー、カメラマン、映像スタッフ、営業・広報(宣伝)マン、物販スタッフ、デザイナー、WEB制作スタッフ、著作権関連の法律に明るいスタッフ、経理スタッフなど、作品作りや日常の活動においては自営業者同様かそれ以上の役割が必要だ。
一人で複数の役割をこなしながら少数精鋭、4,5人でまわしていくようなイメージ。各々がその道のプロフェッショナルだったらなおよい。そしてその際に関わるスタッフは音楽業界の人間である必要もない。音楽の仕事をするためにはレコード会社などに就職しないとできないと思っていた人(特に学生さん)も多いと思うんだけど、レジーのブログのレジーさんや僕は違うルートで縁あって音楽に関わる仕事をしている。(詳しくはコチラの記事を参照)
例えば普段は料理や子供の撮影で生計をたてているフォトグラファーがライヴ撮影をするように、あるいは普段印刷会社で働いている会社員兼デザイナーがジャケットやグッズデザインを手がけるように、普段企業の法務部門で働いている人が権利関係の処理やバンドPR文言の景品表示法チェックを行うといったように。その道のプロがダブルワークでお手伝いをするといったイメージである。
前置きが長くなって申し訳ないけれど、先にあげるような状況を踏まえた上で、その役割の一つには冒頭にも書いた「PR(広報・宣伝)」がある。PRとはパブリック・リレーションズの略であり、バンドの音楽をリスナーに届けたり、リスナーの声をバンドに届ける双方の橋渡しを担っている。僕は他業界で宣伝プロモーションの仕事にも多数携わっており、1年ほど前からその経験を生かしバンドの「パブリシスト」としてお手伝いをするようになった。自分にどこまでのことができるのかは正直わからない。けれど、冒頭にも書いたようにリスナーの立場でできることには限界があると思ったから飛びこんだ。
今回はDIYミュージシャンを広くサポートをしているMCA(一般社団法人ミュージック・クリエイターズ・エージェント)の永田純さんと、音楽配信サイトOTOTOYでパブリシスト講座の講師をしており、かつては洋楽大物アーティストやドリカムなどを担当され、今も多くのインディーズバンドにアドバイスをしている渡邊ケンさんに「これからのインディーズバンドとスタッフの関係、パブリシストの役割」についてお話を伺うことにした。
先ほど業界で働いている人がみんな口を揃えて「大変だよ」と話すと書いた。でもこの言葉には続きがある。誰しもが必ず最後に次の一言を付け加えるのだ。「でも楽しいし、音楽が好きだから・・・厳しくてもやっていきたいんだよね」と・・・今回の記事がインディーズミュージシャンやそのスタッフ、音楽業界で働くことに興味のある人達に少しでもプラスになれば幸いである。
インタヴュー・文 黒須 誠
撮影 ossie
企画・構成 編集部
INFORMATION

みんなの談話室 vol.13
テーマ もう一度考える、ミュージシャンにとってのレーベルのこと、マネージメントのこと。 〜前・P-VINE、現・トノフォン A&R 柴崎祐二さんと語る、今、その可能性〜
ゲスト 柴崎祐二[シバサキユウジ]
現在トクマルシューゴの主宰する株式会社トノフォンにて、アーティストマネージメント並びに制作ディレクターを務める。
聞き手 永田純 [ミュージック・クリエイターズ・エージェント 代表理事]
日 時 2016年6月27日(月) 19:00 OPEN / 19:30 START
場 所 渋谷 カナエル
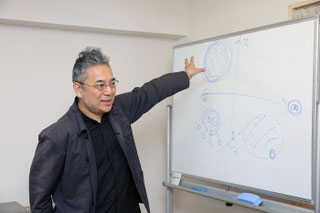
MCAを立ち上げた理由 ~ミュージシャンを主体にした新たな関係作り~

●永田さんがMCA(ミュージック・クリエイターズ・エージェント)、ミュージシャン向けの何でも相談室を立ち上げた理由からお聞かせいただけますか?
永田純 「MCAの設立は2011年です。数年前から、アーティスト一人一人が自己責任、両足で立って歩ける土壌や環境ができているんじゃないかとなんとなく感じていて、それで彼らを後押しできるようなことは何だろうか? ということをずっと考えていたんですね。これまで日本ではミュージシャンとしてある程度のことをやろうとすると、レコード会社やプロダクション、事務所と契約しないとできないことが多いという現実が前提としてあったから、ぼちぼちそれとは別の選択肢と、それを支える仕組みがあってもいいんじゃないか。それも、オープン、ニュートラル、そして信頼性が高い形で、と考えたんです」
●それは意外でした。永田さんはもともと大手のレコード会社はじめ、メジャーシーンで著名なアーティストとも長く仕事をされてきた方なので、そのような方が真逆とも言えるような活動を行おうと思われたことが興味深いです。永田さんがやらなくても個々のミュージシャンが自分たちで考えてやればいいことだと思うんですけど。
永田 「(笑)。今日のテーマからはズレるかもしれないけど、僕はサラリーマンが溢れているこの国が嫌いなんですよ(笑)。何事もそこからしか起こらない、誰も自分で責任とらない感じが。僕の親父は真面目なサラリーマンで、働き詰めて社長にまでなったような人で、ずっといい学校に行け、いい会社に入れと言われて育ったんです。でも70年代初頭にロックを聞き始めてからそれに疑問を持つようになったり、ボブ・ディランが“30歳過ぎた奴は信じるな”と言っていたのをそのまま真に受けて、反抗心を持つようになった(笑)。今でもグレーのスーツ着た人たちが5,6人で群れて歩いているのを見ると石投げたくなっちゃう(笑)。音楽もそういった大きな会社、企業からじゃないと生まれてこないという社会はすごく嫌なんですよ。そもそも音楽作るのは個人だし、それが尊重されない世の中はおかしい。それでなんかできないかなってずっと考えていたんです。まあこれは超個人的な裏テーマですね(笑)」
一同 (笑)
●それは面白いですね。
永田 「僕は“仕事”ということを意識して続けてきたという感覚があまりなくて。東京生まれ東京育ちだから、中学高校のころから下北沢や高円寺あたりをウロウロしていて、それで好きで尊敬できるミュージシャンの手伝いをどうやったらできるかな、ということを考えて、そこから自然に入っていったんですよ。だから、それが仕事になったときもそのミュージシャンとの関係がいびつになるようなことはしたくなかった。例えばいいミュージシャンを見つけて、専属契約書にサインしてもらって、僕が仕事を取ってきて給料を出すというのは、僕とミュージシャンの関係を発展させるものにはならないと感じていたんです。雇用関係、支配・被支配に関係の延長に何があるんだろうな?っていう疑問がね」
●何か具体的な例を教えてもらえませんか?
永田 「例えば、90年代初頭、”たま”というバンドがありました。イカ天ブームのちょっと前から地道に活動していて、彼らは友部正人さんの大ファンで、当時友部さんのお手伝いを僕がしていたので自然に知り合ったんです。友部さんが3カ月に1回ゲストを呼んでイベントをやるという企画があって、青山の円形劇場で一緒にやったりね。当時彼らは“たま企画室”という屋号を持っていて、それが彼らのレーベルでもあって。それでよくある話なんだけど、たまの若いマネージャーが本人たちに内緒でイカ天に応募したら通ってしまって(笑)、出演後の騒ぎはご存知の通り。で、その後たまは筋肉少女帯も所属するような大手のプロダクションから誘いがあって契約することになるんだけど、残念ながらもともといたスタッフはもうその環境では働けないし、そのプロダクションの方にも結局たまの理解者がいなかったのね。それで僕はメンバーから声かけてもらって手伝うようになったんだけど、僕はそのプロダクションから業務委託を受けてアルバムのプロデュースやマネージメントを統括するという形を選んだんですね。そうしていくうちにバンドとプロダクションの距離がますます遠くなって、そのプロダクションに所属している意味も薄れてきてしまって・・・今後どうしようかという話になったときに僕は“もともとの屋号だった『たま企画室』の名前をそのまま有限会社にして4人で役員をやれば?“と提案したんです。つまり、僕は5人目のビートルズでもないし、ビートルズとジョージ・マーティンの関係でもないわけだから、”4人の間に入ることはしないけど、その代り任せてくれるなら雇われ番頭として実務は何でもやるよ“ということですね。要するに、バンドとスタッフの間に信頼関係さえあれば、やり方としてはなんだってありだってことなんですよ」
●それだけ信頼されているスタッフがいる場合は、理想の関係かもしれませんね。ただ今日の話でこの後に出てくるパブリシスト、マネージャーやエージェントといった立場、もう少し距離感があるフラットな立場でやる場合には難しい気がしました。属人的すぎて一般化しづらい気がします。
永田 「この例で大切なのは、誰が主体なのか、ってことです。ミュージシャンが雇用されてプロジェクトが成り立っている場合は、当人たちの理解はどうあれ、実際には会社が主体であることは疑いようがない。で、それしか選択肢がなくていいのか、ってことです。」
●うーん、難しいですね。
永田 「それまでミュージシャンは会社に所属、雇用されるのが一般的だった中で、ミュージシャンが主体で、スタッフに業務委託するという関係はわかりやすかったんですよ。僕が長くおつきあいした別のクライアントの場合は、その方は普段アメリカにいるので、まずその方のための個人会社を一つ日本に作って、そこに権利や収入をすべて集めるようにして、その会社から僕の会社が業務委託を受けるという形にしたんです。これのいいところは、主体と、権利とお金の流れが透明で明確になるというところで、その仕事は15年ほど続きましたが、離れることになったときも基本的には業務委託契約を解除するだけで済んだんですよね。個人会社に権利とお金は一元化されているから、その会社をそのまま新しい責任者に引き継ぐだけでよかったんです」
●それはわかりやすいですね、あとからもめることも少なそうです。
永田 「その通り。音楽を作る人とサポートする人の関係が今のレコード会社や芸能プロダクションがやっているような雇用関係しかないのか、他のやり方があるんじゃないのか。その上で、ミュージシャンが主体になる関係性を構築するためには、彼らが使いやすいサービスを、彼らに近いところに存在させる必要がある。それでMCAを設立したんです」

編集部作成







