本の話をしていると、時折「読書なんて何の役にも立たない」という人を見かけます。
この言葉。半分間違っていますが、半分は正しい言葉なんです。
今回は、そんな話をしていこうかと。
photo credit:Donnie Ray Jones
目次
目的としての「読書」と、手段としての「読書」
読書という言葉には、大きく分けて2つの意味があります。
1つは目的としての読書、もう1つは手段としての読書です。
目的としての読書は役に立たないし、だからこそ価値がある
目的としての読書は、本を読むという行為そのもので読書が完結します。
本を読むこと自体が目的なので、そこから何かを学び取る必要はありません。
読んだ内容はもちろん、読んだこと自体忘れてしまっても構いません。
ただ楽しめればいいし、悲しい気持ちになれればいいし、時間つぶしになればいいのです。
目的としての読書は、娯楽の中の1つに過ぎません。
淡々と過ぎていく日常の中に、彩りを与える方法の1つに過ぎません。

By: Olof Senestam
「目的としての読書」のおかげで人生が豊かになる人もいれば、何が良いのかサッパリ分からない人もいるでしょう。
音楽が好きな人もいれば絵画が好きな人もいるように、百人いれば百通りの接し方があります。そこに優劣はありません。
目的としての読書は、何の役にも立ちません。
そもそも「何かの役に立てよう」と考えること自体が間違っています。
何の役にも立たないにもかかわらず、何故か人を惹きつける。
それこそが、目的としての読書の価値なのです。
手段としての読書は役に立つ
手段としての読書は、読書を通じて得た知恵や知識を使い、問題を解決することによって完結します。
手段としての読書は「先人の知恵を借りることで車輪の再開発をする無駄をなくし、目の前の問題を速やかに解決すること」を目的に行われるので、必ずそこから何かを学び取る必要があります。
学んだことを忘れないように、定期的に読み返す必要があります。
本を読んで得た知恵や知識を使って問題を解決して初めて、手段としての読書に価値が生まれるのです。

By: Richard Walker
たとえ1000冊分の「手段としての読書」をしたとしても、そこから得た知恵や知識を何1つ使わずに「なんか偉くなった気がする」で終わってしまったら、その読書は娯楽本を読んでいるのと何の違いもありません。
むしろ、人を楽しませるための感覚が身につく分、娯楽本の方がよっぽど価値のある読書と言えるでしょう。
家に帰るまでが遠足であるように、その知恵や知識を使って問題を解決するまでが読書なのです。
知恵や知識を手に入れる事で、目の前の問題を解決していく。
それこそが、手段としての読書の価値です。
手段としての読書によって社会は発展してきたことからも分かる通り、手段としての読書には高い価値があります。
しかし、カッコつけるために偉そうに読書をしていても、その読書を通じて何も学び取らず何も解決できないのなら、そんな読書には何の価値もありません。漫画を読んでいる人の方がはるかに優れた読書家と言えるでしょう。
それぞれ向き合い方が全く異なる2つの読書
このように、2つの読書は目的も価値も全く異なるので、当然その向き合い方も大きく変わってきます。
目的としての読書であれば、本人が一番良いと思う好きな読み方をすればいいのです。
一字一句残さず暗記するのも、適当に読み飛ばすのも勝手です。
他人から強制された読み方では、その人にとって最大限に本を楽しむことはできなくなります。
目的としての読書において、他人の読み方をどうこう言うのは無粋としか言いようがありませんし、「自分はこう読書しているんだ」と偉そうにするのも無粋としか言いようがありません。
ただ読書を楽しみ、著者に感謝する。それだけです。

By: Philippe Put
一方、手段としての読書であれば「どう読めば、この本に書いてある知恵や知識を最も効率よく吸収できるか」を考える必要があります。
本の読み方を勉強する必要もあるでしょうし、部下に本の読み方を指導することも重要になって来るでしょう。
勉強やスポーツもコツをおさえた練習をしなければいつまで経っても成果が出ないように、手段としての読書もコツをおさえ、型を身につけなければ「カタ無し」になってしまいます。
手段としての読書を通じて何か成し遂げたいことがあるのであれば、読書を通じた勉強をする前にまず読書の仕方を勉強しなければなりません。
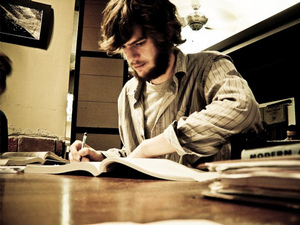
By: mer chau
文学・歴史の本は、目的としての読書なのか手段としての読書なのか
例を挙げるなら、小説は目的としての読書であり、実用書は手段としての読書と言えるでしょう。
ただ、ここで問題になるのが文学と歴史です。
文学や歴史などは教養を身に着けるために読むものであり、読んですぐに何かの役に立てるのは非常に難しいものです。
そういう意味では、目的としての読書に近い部分もあります。
しかし、文学や歴史の書物はそんな近視眼的な思考で読むものではありません。
文学や歴史は「なんの役にも立たないかもしれないけど読み続けよう」と長い年月をかけて積み上げてきた教養が、十数年の時をかけて初めて役に立つものなので、非常にレベルの高い「手段としての読書」になってきます。
そういう意味では、実用書を通じて「手段としての読書」のコツをおさえた上で、長期的な視点から少しずつ文学や歴史の本に手を出していくのが、一番効率の良い読み方と言えるのではないでしょうか。
手段としての読書のコツを学ぶには
手段としての読書とは勉強です。それも、答えのない勉強です。
勉強の仕方にもコツがあるように、手段としての読書にもコツがあり、コツをおさえておかないと読書は「何の役にも立たないもの」に成り下がります。
レバレッジリーディングのような「本を読むための本」を読んだり、様々な書評ブログで「本を読むときのコツ」に関する記事を読むなどを通じて少しずつ読書のコツを学んでいくことが、読書の価値を高める唯一の方法だと、ぼくは思います。







