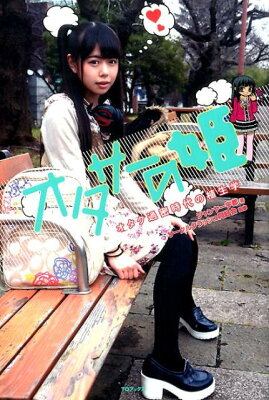2015年10月27日
大分以前に買った本で内容覚えてなかったり
積読してて読んでない本も紹介しちゃうかもしれないけどよろしく
順番は何となく目に付いた本から
推理小説が多めになると思われる
和辻哲郎「日本精神史研究」
大分以前に読んで本で内容はほとんど覚えていない
薄い橙色に青のラインが入ってる背表紙で目が付いた
時代ごとの文芸、美術作品なんかから、その時代ごとの日本人のメンタリティを論じた本だと思う
めくってみると竹取物語、源氏物語、仏像、歌舞伎なんかが述べられているようだ
名著と言われているので再読せねばならない本の一冊である
>>4
なんか面白そう
他のも期待
アントニイ・バークリー「毒入りチョコレート殺人事件」
推理が推理を呼び、推理を呼ぶ。そして最後には謎が残る
そんな古典推理小説の名作の一つ
犯罪研究会の方々が順々にリレーのようにチョコーレート毒殺事件の推論をしていくお話
梶井基次郎「檸檬・Kの昇天 ほか十四編」
「檸檬」は確か高校の教科書にも載っていた気がする
今の高校の教科書にも載っているのだろうか
情景描写が簡潔かつ緻密というか綺麗な文体だと感じる
「檸檬」の最後に灰色の世界に鮮やかな色彩が加わる感じ
「桜の樹の下では」の桜の光と闇の濃淡が好みではある
ジョセフ・E・スティグリッツ「スティグリッツ教授の経済教室」
週刊「ダイヤモンド」での連載を書籍化したものだった気がする
著者はノーベル賞も取っている経済学者
2000年代半ば頃の連載をまとめたのが世界や各国の経済予想が結構当たっている
アメリカが強力に推し進めるグローバリズムに懐疑的な論調
日本が今アベノミクスでやっている量的緩和をするしかないだろうとも確か述べてた
詳しく語るには内容忘れた+経済詳しくないのでこれ以上は無理w
近藤唯之「プロ野球 痛快ライバル論」
90年代前半かな?に書かれているのので、
語られてるのは与田剛VS野茂秀雄、清原和博VS秋山幸二等など
著者は確か長らくスポーツ紙の記者をされていた方で、与太話やエピソードで選手の性格なんかを語っていくスタイル
非常に特徴がある文体、言い回し。かつて延々真似してレスするスレが野球板だったかな?にあったくらいw
ジャンル幅広いなあww
ウィリアム・ゴールディング「蠅の王」
少年達が無人島に漂流したら…
助け合って仲良く生活するかって?
そんなはずないじゃんwwwみたいな話
バトルロワイヤルとか漂流教室的な感じになる
と言うか、その手の恐らく元祖的な作品かな
>>13
骨肉の争い!
これ面白そう!
麻耶雄嵩「鴉」
現代社会と隔絶されている村に語り手が迷い込み殺人事件に出くわす
ちなみに村から出ようとすると鴉に攻撃してきて脱出を拒むっていうのが隔絶している理由
詳しくはネタバレになるから書けないが最後のパッと視界が開ける感じが好き
作風が全く違うけど伊坂幸太郎の「オーデュポンの祈り」の最後も似た感じでやはり好きである
『「古事記」と「日本書紀」の謎』
上田正昭、岡田精司、門脇禎二、坂本義種、園田香融、直木考二郎
大学の先生達が「古事記」と「日本書紀」の謎について述べている
記述の違いのWHYや日本書紀に添えられていたが散逸してしまった系図の内容の推論など
一般人向けに書いて頂いているのだとは思うけど、個人的には難しい内容
武烈天皇の暴虐記述=中国の王朝末期の皇帝は暴虐を限りをつくしたことにするあれ
からの王朝交代論?に言及されていたのは面白かった
>>17
本棚の趣味が似てるかも。好きな本の関連作品は全部並べる
筒井康隆「最後の喫煙者」
短編集。筒井康隆の短編はドタバタというハチャメチャで皮肉というか煽り?が効いているものが多い
表題作は喫煙が完全禁止になり、喫煙者がゲリラ的に抵抗し、主人公は最後に残った一人となり…
そんなお話。同調圧力だったり、禁煙団体のヒステリックな感じが書かれていて面白い
ターザンが観光産業で金持ちになって老人になってもまだ金のためターザンやっているって話も面白い
捲ってみたんだけど、この本短編傑作集の模様
宮城谷昌光「孟嘗君」
鶏鳴狗盗なんかの故事で知られる戦国四君の一角、孟嘗君のお話
孟嘗君は紀元前3世紀頃、中国が戦国時代だった時の斉の王族
漫画のキングダムより数十年前に活躍していた人
作者が春秋戦国時代の英雄を書く際は、その英雄の有名な事績に至る前を書くことが多い
父の話や出生、若かりし頃は資料が少ないわけだが、そこは作者の中国史や漢字の知識で補って語られる
好人物が多く登場して爽やかな英雄譚
戦乱の世の英雄なので後ろ暗い点も多々ある人なのだか宮城谷昌光氏にかかると必ずラストは爽やかな風が吹いている風に落ち着くというw
ちょうど10作紹介したか…
見てる人いるか分からんけど、一端中断して夕方以降に再開しようと思っています
完全なる自己満スレなんで板汚し失礼してます
再開待ちwktk
人の本棚って面白いよね〜
伊達龍彦 『五人の女教師 悪魔学園』フランス書院
再開
泉麻人「泉麻人のコラム缶」
ナウいなんて言葉が流行っていた80年代のバブリーな時代に書かれたコラム集
こんなのが若者達の間で流行っている事柄を紹介したコラムが多い印象
バブル時の流行が分かるという意味ではバブル未経験者にとっては興味深い一冊
バブル時に青春時代を過ごした方々は懐かしい一冊になると思われる
北方謙三「楊家将」
北宋初期の軍閥、楊業やその息子達が描かれている
楊一族は元々北漢に属していたが宋に降り、宋の北に位置する強国遼との最前線を担うことになる
中国の古典文学「楊家将演技」がモチーフらしいが、大分改編されているらしい
楊家の長、楊業を筆頭に宋と遼、戦う男達の生き様が交錯する熱い物語
作中に出てくる羊料理が美味しそうなことが個人的には印象に残っている
大下英治「政商」
昭和闇の支配者シリーズの二巻
この本が目に止まったので一巻を探してみたがなかった
「政商」は「記憶にございません」で有名?な小佐野賢治の生涯を描いている
一巻の「黒幕」は確か児玉誉士夫
事業家としての顔、フィクサーとしての顔、様々なエピソードが紹介されている
刎頸の友の田中角栄はもちろん、五島慶太、小林中等など昭和の大物たち勢ぞろいといった印象
ちなみに小佐野賢治が創業した国際興業はバス事業を手広く手掛けている総合商社
一時は経営不振でハゲタカファンドに買収されたりしていたが、今はどうなんだろうか?
鯨統一郎「邪馬台国はどこですか?」
歴史ミステリの短編集
基本的にはバーで常連客が表題の邪馬台国があった土地や本能寺の真相、聖徳太子の正体等を推理していく
異説、珍説が最終結論となる場合がほとんど。結論の突飛さとそこに至るまでのロジックが魅力
専門家から見たら突っ込みどころ満載なのかもしれないけど面白くてそこそこ説得力あれば別に良いよね
面白くてそこそこ説得力あればいいよねにクソワロタwww
司馬遼太郎「夏草の賦」
長曾我部元親とその夢で明智光秀の家臣斎藤利三の妹、奈々の話
土佐から四国を平定していく様
四国を攻略せんと攻めよせてくる豊臣秀吉の軍勢で物量、戦術、謀略全てで敵わず秀吉に完全屈服する様
期待していた息子と奈々に先立たれて英雄としての覇気を失ってく様
爽快さもあり、もの哀しくもある四国の英雄の可能性と限界が描かれている本
泡坂妻夫「しあわせの書―迷探偵ヨギガンジーの心霊術」
跡目継承問題で揺れる宗教団体の信者失踪問題に迷探偵ヨギガンジーが解決に乗り出す
そんなお話だけど、ぶっちゃけこの本のストーリーはおまけ
メインのトリックと言って良いのかすらも分からない仕掛けを堪能するミステリ
最後まで読めば、多くの人は驚愕するはず。一部の人はキレるかもしれない
個人的な感想は、作家ってすげー
原りょう「そして夜は甦る」
りょうは寮のうかんむりがない字だけど変換できなかった
ハードボイルド小説。文体は翻訳っぽい感じ
ストーリはミステリ的にも面白かった気がする
気がしているだけで完全に忘れています
面白かった気がするので再読せねばw
本屋で見たらそうでもないが
他人の本棚にあるというだけで面白そうに感じるな
それでは明日気が向いたらまた紹介します
完全に自己満足というか再読する本の確認になってますw
おつ!
気が向いた時を楽しみに待ってますー!
村上春樹「回転木馬のデッドヒート」
村上春樹の短編集
村上春樹の作品は全部読んだわけではないけどこれが一番好き
そして俺の生活に影響を与えた一冊である
とある短編で鏡を見れなくなった男が出てくる
鏡を見ないで手触りだけで髭を剃るのは苦労したらしい
やってみる→いけうやん!→鏡を見ないで髭を剃るのがデフォに
鏡を見ずに髭を剃らなくなってはや10年以上の歳月が経過している
つまり、俺に髭の剃り残しがあったっとしたら、その原因の幾ばくかはこの本にある
鳥越憲三郎「出雲神話の誕生」
大学の先生が1960年半ばに書かれた本を文庫化したものらしい
日本神話の中で重要な位置を占める出雲神話
何故出雲が重要な位置を占めているのか?を論じた本
古代出雲に大勢力は存在せず、どちらかというと後進地域であった
出雲の神々は高天原の神々の裏、対峙するような裏方とも言える存在である
大和朝廷の勢力下であり僻地でもあった出雲という土地が裏方として選ばれた
他にも様々な考察が述べられるが大筋としてこんな感じである
荒神谷遺跡の発掘でこうした説は一掃されてしまうわけではあるが、
その前の歴史学者の出雲への見解を知るという意味では興味深い本
様々な資料をもとに考察されているようで、その論は緻密で面白いです
クレイトン・クリテンセン「イノベーションのジレンマ」
大企業が何故技術革新により廃れてしまうのか?が論じられている
大企業は顧客の声を聞き、資金を投下して既存の製品をより魅力的なものにすべく日々励んでいる
一方、技術革新は、例えば、かつてのデジカメのように、欠点があり陳腐なものであることが多い
結果、大企業は技術革新を軽視してしまうが、徐々に新しい価値を提供するイノベーションに市場が席巻され大企業が磨いてきた技術の価値はなくなり力を失っていく
例えば、フィルムカメラに対するデジタルカメラのように、営業所を展開する証券会社に対するネット証券にように
経営学に全く詳しくない俺の理解ではこんな感じ
何らかの製品で高いシェアを占めていた大企業が技術革新を前に力を失う例がたくさん紹介されています
頭悪くて理論が理解出来ない俺には、お話としてこちらが面白かったですw
個人的には、インシュリンでイーライ・リリーがノボにやられた事例が分かりやすくて、こーいうことねと思いました
西尾維新「クビキリサイクル」
化物語なんかで知られる著者のデビュー作
本作は全10作に渡る戯言シリーズの第一作目である
トリック?も少し捻ってあるし、まあミステリです
でも、この方の作品はキャラクターと掛け合いに魅力があるのだろうか
ミステリ界の大物新人だと思って買っていたのでシリーズが進むにつれミステリ要素が消えていくのは個人的には残念だった
しかし、語り手いーくんの本名って結局なんだったのだろう?
それでは明日気が向いたらまた紹介します
見ている人がいるのか分かりませんが、良い夜を
ほんとんどの本を読んでみたくなる不思議
お疲れ様
全裸待機
原田宗典「0をつなぐ」
短編集
世にも奇妙な物語の題材になりそうな、ちょっと不思議な話が多い
日常が崩れ非日常に片足を突っ込みつつある語り手の不安な心理描写?がテーマな雰囲気の小説
どれも不思議だったり、稀な偶然があったりで語り手の心をざわつかせる
「ビデオテープでもう一度」という短編が収められているが
ストーリーは覚えていて、何故か村上春樹の短編だとさっきまで思っていた
何故なんだろうw
おかえりー!
村上春樹と文章が似てるのかな
今日は何冊紹介してもらえるんだろ!
鈴木大拙 著 北川桃雄 訳「禅と日本文化」
仏教学者鈴木大拙が英語で記した本を和訳した本
鈴木大拙は禅を海外に紹介した仏教学者として知られている方
内容は禅と美術、禅と茶道、禅と俳句といった具合に日本文化の奥底にある禅の思想について論じたもの
15年程前に読んだ本なので詳しい内容は忘れました
が、もともと外国人向けに書かれた本ということもあり、理解しやすかったという印象だけ残っています
禅は不立文字なので読んで分かるものではないと思うのだけれど、
凡人は本でも読んで分かった気になれば十分な気がしないでもない
最近、日本は凄い的な本が流行っているらしいけど、それならこういった本読むほうがよくね?と思ったりしますw
ってことで、この本も再読しなければならない
天藤真「大誘拐」
昭和傑作ミステリ選をやったら必ず入るであろう本作
個人的にも日本ミステリ五指に入る出来だと思う
少し抜けた三人組が田舎の富豪のお婆さんを誘拐
間抜けな三人組に頭脳明晰なお婆さんがたまらず口を出し、主導権を握られ…
身代金はなんと100億円。そんな誘拐の結末や如何に!?
身代金や動機の点で驚きはあるけれど魅力的な謎で引っ張るタイプの本格派ではない
最後はそうだったのねとはたと膝を打つ真犯人?の独白あり
度胸満点、頭脳明晰、誘拐されたお婆さん、柳川とし子刀自の無双っぷりを堪能するミステリです
小松左京「日本沈没」
有名なSFの傑作
日本列島が沈没してしまうお話です
日本列島が沈没する原因は科学音痴の私には十分に説得力があるものであり
近未来的な描写もあるけど基本的には1970年
極めてリアルな大災害シミュレーション物語として恐ろしくも面白い一冊
ちなみに、日本以外全部沈没という短編を筒井康隆が書いています
「日本沈没」は日本人の気高さみたいなものも描写してますが、こちらは島国根性みたいなのを煽ってますねw
それでは明日気が向いたらまた紹介します
見ている人がいるのか分かりませんが、おやすみなさい
おやすみ
年齢は30半ばくらいかな?
高城彬光「成吉思汗の秘密」
歴史ミステリの傑作
名探偵・神津恭介が義経=チンギス・カンを証明するといったもの
読む限りでは精緻な推論がなされているように思える
専門家から見れば笑止千万なのだろうが
浪漫溢れる推理にうっとりなる一冊
発行後に追加されたエピソードが浪漫溢れる余韻を残す
やはり、これも詳しい人から見たら完全に間違っている解釈らしいけど…
歴史が好きで面白ければ良いじゃないって人にはお薦めしたい本
陳 舜臣「小説十八史略」
全6巻
尭、舜、禹の三帝から始まり、南宋が滅びるあたりまでの中国史がざっくり分かる便利な本
その時代ごとの英雄たちのエピソードが中心になっており、中国史をなぞりながらも極めて小説的な内容
三国志が日本では有名だけど、それ以外の時代も面白そうだなと人によって興味を持つきっかけになるかも
ちなみに俺はそうでしたw
吉村正和「フリーメイソン」
著者は西洋神秘思想史専攻の大学の先生
人生においてフリーメイソンが気になる時期ってありませんか?
俺はありました。そんな時期に購入した本です
様々な資料をもとにフリーメイソンの歴史、理念、儀礼等について解説がなされている
陰謀論的な観点はあまりなく、あくまで確実なことだけを書いている感じ
あくまで入門書的な位置づけの本作
よく分からないけどフリーメイソンが気になるという中2病の方は読んでみてはいかがでしょうか?
それでは明日気が向いたらまた紹介します。グッナイ
もうそろそろかな
パウロ・コエーリョ「アルケミスト」
完全なる積読本です
10数年前に知人に勧められたのですが、数ページだけ読んで放置しています
翻訳ものだからか読み辛かったのでしょう
感動する話らしいです
この本は面白いのでしょうか?
誰か情報下さい。お薦めならページ数も少ない本なので読んでみようと思います
開高健「夏の闇」
闇三部作の二作目。確か三部は未完
一部の「輝ける闇」は読むべきなのに読んでませんw
「輝ける闇」は主人公が従軍記者としてベトナムへ行った際の話
開高健の経験がもとになっているらしい
二部目の本作は、ベトナムで廃人っぽくなった主人公がフランス、ドイツへと渡り
女と共にひたすら寝て酒飲んで食ってする話
眠気を感じる描写、睡眠で意識を失う描写が極めて上手で眠くなる小説です
最後生きる気力を取り戻します
ヨースタイン・ゴルデル「ソフィーの世界」
少女が哲学者に哲学の歴史についてレクチャーを受ける話
少女ソフィーが哲学を学びながら自分は一体誰なのか?存在しているのか?を問うていきます
簡易的な哲学の歴史やそれぞれの哲学の思想に触れることができます
難解な哲学を相当簡単に説明しているようなので、あくまで入門書の入門書レベルなのでしょう
物語としても面白く、哲学史の講義が現代に近付くにつれて、紹介される思想が物語に絡んでいきます
自分の存在があやふやになっていく感じは、ドグラ・マグラや世界の終わりとハードボイルドワンダーランドなんかに通じるものがあると思いました
哲学に興味がある人にはおすすめです
さて今晩はここまでです
良い夜をお過ごし下さい
遅くまでおつでした!
今日の本もきになるけど、大誘拐のおばあちゃんが頭から離れないww
さて1日ぶりに淡々と書いていきます
金谷治 訳注「孫子」
春秋戦国時代の呉の兵法家、孫武が著したと言われている兵法書
13編に分かれている今の我々がよく見る形に編集したのは三国志時代の曹操らしいです
勝者の民を戦わしむるや、積水を千仞の谿に決するが若き者は、形なり
準備って大切だよね的な意味です。積水化学の社名の元ネタですね
紀元前に書かれていた兵法書ですが、今でも様々な人に読まれています
兵は軌道なり
敵を知り己を知れば百戦危うからず
意味もなく使ってみたくなる言葉が満載です
戦争を哲学?している孫武の思想を考えるのも面白い良書です
夢野久作「ドグラ・マグラ」
・・・ブウウ―――ンンン――ンン・・・・・・・・・。
有名な作品です
文庫版の表紙がとても素敵で思わず二度見してしまう
そんな本です
読むと気が狂うとか色々言われていますが、内容、文体とも独特でとてもピーキー?な本という印象
特に中盤、登場人物の博士が記した一風変わった論文?がひたすら続き、そこが辛かった
今ではむしろそこが好きなのですが、初読の時はそこで一端投げています
記憶を失い病室で目覚めた男が記憶を取り戻そうとするというのが話の筋です
男は徐々に幻覚なのか現実なのか判断できないものを見るようになり、混乱をきたしていきます
一応ミステリにジャンルされているのは、男が殺人事件に関わっていそうなこと、また男は誰なのか?というのが話の骨格にあるからなのでしょう
現実と幻覚が絶妙にまじりあい、読者をも混乱へと巻き込んでいきます
酒を飲みながら静かな夜更けにじっくり読みたい本です
・・・ブウウ―――ンンン――ンン・・・・・・・・・。
あら良スレ
和辻哲郎に鈴木大拙とはまたなかなか…!
ご専攻は何です?もしかして理系?
北村薫「ターン」
主人公が交通事故に遭ったのをきっかけに交通事故の前日をひたすらループする話です
世にも奇妙な話でも確かうっちゃんなんちゃんの内村が主演した回で似た話がありましたね
あちらは現実世界をループするのに対して、こちらは自分以外に誰も存在しない世界です
当然、主人公は明日に戻るべく試行錯誤を繰り返すというのが本書の主題?になります
爽やかな感動する話ですね
自分以外は誰も存在しない世界と書きましたが、実は明日の世界へとも僅かに繋がっていたりします
似た話を知らないなら、誰が読んでも面白いのではないでしょうか?おすすめです
サイモン・シン著 青木薫 訳 「フェルマーの最終定理」
「n > 2の時、xn + yn = zn となる x, y, zは0でない自然数の解を持たない」
これがフェルマーの定理です。そしてこの定理は300年以上証明されないでいました
17世紀に定理が誕生してからアンドリュー・ワイルズによって1995年頃?に証明されるまでが書かれています
数学の歴史を解説するとともに、この定理が証明されるまでの360年間の様々な数学者の生きざま、研究成果が紹介されています
正直、数学は苦手で紹介されている様々な理論は全く理解できませんでしたが、非常に面白く読めました
巨大な謎に数多の数学者が立ち向かっていく、熱くさせる本です
私が理解できなかっただけで、数学の解説も分かりやすく数学苦手な人にも分かりやすいように書かれています
今晩はこれまでです。良い休日を
アイザック・アシモフ著 池 央耿 訳「黒後家蜘蛛の会1」
ミステリの短編集です
全編とも週に一度レストランに集まり謎について喧々諤々議論するサークル内の話を描いています
メンバーは、学者や画家、作家、弁護士等など、何人だっけかな?6〜7人くらいです。
横で聴いていた給仕のヘンリーが鮮やかに謎を解くというパターンに則って常に話は進みます
テレビドラマ水戸黄門のアームチェアディテクティブ短編版とでも言えばよいのでしょうか
ちなみにアームチェアディテクティブとは、邦訳すると肘掛け椅子探偵かな?
まあ、椅子に座ったまま、聞き取り捜査なんかをせずに聞いた話なんかをもとに推理するタイプの探偵のことです
良編もあるし、いまいちな感じなのもあるけど、全体的にヘンリーが素敵です
連城三紀彦「戻り川心仲」
恋愛小説作家として有名?な作家さんです
ですが、デビュー時はミステリ作家
本書も昭和ミステリ史に残る傑作短編集と言われています
何より文章が流麗というか上手
描かれている時代は大正〜昭和初期くらいかな
全編花がモチーフになっており、美しくも陰鬱で儚い感じがするお話が多く収められています
ミステリ的には動機や殺人に至った経緯の解明が主眼に置かれている感じです
まあ、傑作ミステリと言われていますですが、これミステリ?と思う方もいるかもしれません
でも、良作です。上手な文章を読みたいという方はこの本読むのもよいと思われます
岩崎夏海「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」
何年か前の話題作
病気の友人に変わって色々と問題を抱える野球部のマネになったJK
勘違いからピーター・ドラッカーの「マネジメント」を購入してしまうのだが、
マネとしての仕事にも生かせることに気付き、「マネジメント」を参考に野球部の問題解決に取り組んでいく
こんなお話です
病気の友人、問題を抱える野球部員、やる気のない顧問、奮闘する主人公、これをもとにストーリを想像してみて下さい
恐らく、大体あっていますw
ストーリーも陳腐ですし、文体も「〜は〜と思った。〜だった。」みたいな感じで平易ですが、プロ作家っぽくないです
肝心の「マネジメント」の入門としてもいまいちな感じ
「マネジメント」自体、実践するのはともかく理解するのが難しい本ではないので、これ読むなら「マネジメント」読んだ方が早いと思われます
企画って大事だなあと実感するのに最適な本です
おっ。アシモフさんでSFではなくミステリーを選ぶとは…!
アームチェアディテクティヴは日本語では安楽椅子探偵と訳されることが多いかな
井上ひさし「私家版 日本語文法」
ひょっこりひょうたん島なんかで有名な方の日本語エッセイ
広告、古典、新聞記事、法律、野球場の野次等などを参考に文法の変遷なんかが軽妙に語られています
文法を切り口に日本人の意識へ言及してたり、軽い感じで語りながら作者の鋭い視点も感じられます
とても面白いので、日本語に興味がある方は読んでみて下さい。良書です
レイモンド・チャンドラー 著 清水 俊二 訳「 長いお別れ」
ハードボイルドの金字塔
が、内容をほぼ忘れてしましました
確か飲み友達が自刹して真相を追う的な話だったような…
最後が「警官とさよならを言う方法はまだ発明されていない」で〆られてカッコいい感じを醸し出していたのは覚えています
謎解きというより、探偵フィリップ・マーロウのカッコよさや洒落た言い回しなんかを堪能する小説です
内容を忘れてるんで本当は何も言ってはいけないんですけど
再読しなければならない一冊です
それではまた明日か明後日にでも
残り少ないですが、良い休日を
お疲れ様。
期待age
外山滋比古「フィナーレの発想」
英文学者、言語学者、評論家、エッセイスト等、マルチな才能を持つ方のエッセイ?です
内容は自己啓発的なもの
人生のフィナーレをどう迎えるか?を主題にどう日々を過ごすべきなのか著者の私見を述べています
読書の仕方、休み方、暇の作り方・つぶし方等など、長い人生どう充実させるのかのヒントが詰ってます
自己啓発的な本はほぼ読まないのですが、何故か手元にあるこの本
記憶を辿ると学生時代、父か母から読めと進められたような気が…
辻 仁成「そこに僕はいた」
芥川賞作家でミュージシャン
南果歩と中山美穂の元旦那のエッセイです
小学〜高校の頃までの数々の友人達とのエピソードが綴られています
こんな奴いたわwwとか、似た体験したわwwとか、個人的には頷ける話が盛りだくさんでした
ちょっとセンチメンタルな語り口で、昔が懐かしくなる一冊
初読は高校生の頃でしたが、今読むとまた感想が変わる良い本です
高橋 克彦 「総門谷」
SF伝奇小説です
凶器として活用できそうな分厚さです
内容は前半部分は、東北で発見された焼死体と頻繁に目撃されるUFOの謎を出版社の面々が追うといった内容
スケールの大きい謎に刻一刻と迫っていく展開に惹きこまれてページを捲る手が止まらなくこと請け合いです
そして後半、ストーリーは急展開し、世界観が崩壊というか超新星爆発というかビッグバンというべきなのか…な感じになります
筒井康隆の長編によくあるような展開を笑いなし、毒なしで極めて真面目に描いた感じと言えばよいのでしょうか?
後半の展開を受け入れられる方にとっては、傑作です
前半の数々の謎が絡みあってく展開だけなら完全に傑作と言えるのですけど…
今晩はここまで
おやすみなさい
お疲れ様!
楽しく拝見しています
おやすみなさい
この記事へのコメント
センスいいと思う
短い文章でどんな本か何となく伝わる
みんなが見てる
コメントする
卑猥な単語や誹謗中傷コメントは修正される場合がありますのでご了承くださいm(__)m