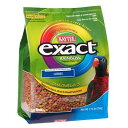カメラというものに日常的に触るようになったときに
色々使っていった結果手にしていたのはいつしか、
防水仕様で大きくて重くてごつくて、
砂の入る隙間のないいわゆる工事現場用カメラでした。
その後に就いた仕事がこれまた建築現場関係だったので
やっぱり用意されるのはいつも、泥がはねようが
雨が降ろうがびくともしない広角レンズならぬ甲殻ボディを持つカメラ達。
だから私のカメラに対するアプローチは、知らない間に
とってもぞんざいになっていたようでした。
・・・以上言い訳をのべたのは、
つまりは普通のデジタルカメラを持たせると、
二年で破壊させてしまう私に対するスタッフの怒りへの言い訳を
頭の中で繰り返し反復練習している私の今のせりふなのであります。
私はまたまた、前回の修理から一年足らずで
カメラのフロントカバーがはずれ、液晶が映らないという
もうぼろぼろの状態にしてしまいました。
それでもシャッターを切れば、カシャッといって撮れるのですが
さあて、一体何が撮れてるやらで、
スタッフ曰く
「これはデジカメではない!」
・・・・ごめんなさい・・。
久々にオスカルを撮ったまではよかったんだけど
その後何があったのかな。。
そういやカバンに入ったまま、そのカバンを野ざらしにしたり
解体現場に立ち寄ったときにその辺に放り投げたりしたっけな。
うーん・・・。
というわけで、現在新しいカメラを買うか、
修理に出すかですんごく悩んでいるのですが
次に欲しいのは断然一眼レフデジカメなので
ちょっと手が出せない値段に尻込みしています。
というわけでしばらくは、どっかからぱくってくるまで
写真がのせれないかもしれないので
今日は気になる鳥ニュースを書いてみました。
それは、先日の親王誕生から過熱している、
秋篠宮家関連のニュースから。
秋篠宮といえば、芸能人もお参りに通うという
奈良の芸術の神様でありますが、
すぐ隣に競輪場があるので
お参りに行った後の清廉粛々とした気持ちが
「今日は決めるぞ ゴラァ!」とギラギラした目つきで
気合の入ったパンチパーマのオッサン達の群れに出くわす確立が高く
一瞬にして粉砕されるというムードのない場所にある神社。
かなり規模としては小さい神社なので
そこの名前をもらわれたときはすごく意外でしたが
それにしても素敵な名前です。なので私は
とっても芸術好きの方なのかなーっと思っていたのですが、
殿下は以外にも、鶏の研究者だったのですね。
というのも、秋篠宮邸はさながら小さな動植物園のようで
たくさんの動物が鶏を筆頭に暮らしているのだとか。
眞子様 佳子様も鶏に餌をやって世話をしていたというから
これまた驚きです。
今の時代に、鶏肉は毎晩食べるのに、
生きている鶏に触ったことのある子供なんて
どれだけいるでしょうか。
スーパーのパックになった鶏肉が、一体どこの命をもらって
店頭に並んでいるかを知っている子供なんて
そうはいないと思います。
まあ、逆に宮様はそんなパックの鶏肉など見ないでしょうが・・。
鶏が卵を産んで、その卵がひよこに孵って。
自然の命のサイクルを感じるのに、最適な環境でお育ちのようです。
なんと私が大好きなカピバラまで飼っておられたことがあるとか。
今でも鳥獣類に囲まれて、世話をされているなかに
新親王が加わられるのは、とても微笑ましい限りです。
そんな中で、気になるのが「天草大王」という鶏。
これはこんな鶏だそうですが
なんと背丈が90センチもあるのだとか!
大型犬なみの大きさの鶏に
餌をやる秋篠宮一家・・・うーん、想像できません。
しかしそれだけ大きいと貫禄があってかなり格好良い。
そりゃあ由緒ある珍種なのだろうなあと調べてみると
これまた驚いたことに全部鶏肉業のサイトばっかり出てくる。
どうやら水炊きにいいんだとか・・・。
こんなに珍種でも所詮は鶏なんですねえ。
やっぱり日本人はなんでも食べる人種なんだ・・・。
私はてっきりマニア向けに飼育されてる
ショー鶏の一種なんだと思っていました。
調べるとこんなかんじでした。
↓
かつて肥後の国・熊本県では、かつて「肥後五鶏」と呼ばれた5種類の鶏が数多く飼育されていました。肥後五鶏とは「天草大王」「熊本種」「地すり」「久連子鶏《くれこどり》」「肥後チャボ」を指し、県内で独自に作出された地鶏です。これらの鶏は農家の庭先飼いとしてごくポピュラーな存在でしたが、普及種による養鶏が大規模化するに従って徐々に姿を消し、昭和40年代に入ると、絶滅や絶滅寸前にまで追いこまれるようになりました。
熊本県ではこうした状況を危惧し、昭和51年に肥後五鶏の保存会を設立。養鶏試験場を中心に種の回復に努めてきました。わずかに残った種の増殖や雑種とのかけ合せなどの研究を重ねる中、「熊本種」「地すり」「久連子鶏」「肥後チャボ」の作出に成功。残る「天草大王」の復元のみが、その後の課題として持ち越されることになりました。
「天草大王」は、明治時代に輸入された中国原産の「ランシャン種」に、天草地方で飼育されていたシャモやコーチンを交配させた肉用種。その体はとても大きく、雄の最大のものでは、体重が6.8キログラムという記録が残っています。地鶏特有のかみごたえのある肉は深いうまみを持ち、福岡県へ「博多の水炊き」の材料として出荷され、高値で取引きされていました。しかし、大型種のため産卵率が極めて低く、昭和初期にはすでに絶滅したといわれています。
「肥後五鶏の中でも、『天草大王』の復元が難しかったのは、絶滅してから長い年月が経ち、文献や写真などの資料が乏しかったこと。さらには原種である『ランシャン種』の入手が困難だったことが上げられます。いちど絶滅した種を復元するには、1年1世代の交配と飼育を繰り返し、成鶏の状態を細かく検定する以外に方法はありません」と、熊本県農業研究センター・畜産研究所の松崎正治さんは語ります。
同研究所では平成4年に、希少な「ランシャン種」をアメリカから100羽輸入し、「天草大王」復元の研究に着手。7世代交配を経た平成12年度の成鶏の検定結果を踏まえて、翌年に「天草大王」復元に成功したことを正式発表しています。昭和初期に絶滅して以来、約70年ぶりの復元となりました。
というわけで、ここからは皇室と復元というものについて
昔少し勉強したことがあるので気になったことを書くと
つまりは、復元ということで、本物の天草大王は
絶滅して、種も保存されていなかったということですよね。
元々博多水炊きのためにランシャン種を中国から取り寄せて、
品種改良してサイズを大きくして天草大王って名づけたけど
水炊きの需要が減って、明治中期にできたのに
昭和初期の間で絶えちゃったのですね。
種の保存もできなかったんでしょうね。
だからもういっかいランシャン種を取り寄せて交配すりゃ、
同じものができたということなんだけど、
それが現在では熊本県のブランド地鶏として
はばをきかせているらしい。
日本最大級の地鶏だということですが、
味はとにかく肉質が柔らかくて最高だそうです。
私も子供の頃にひよこ釣りの屋台で取ったひよこを
3羽育てていましたが
ある日学校から帰るとすきやきになっていました。
しかも大して良い餌を与えていたわけではないので痩せていて
ちっとも美味しくないのが悲しくて悲しくて
なんのためにこの子達は生まれてきたんだろうと真剣に嘆いた。
それ以来鶏は飼っていないのですが、たまに(大人のクセに)
「動物のお医者さん」を読むと、無性にまた飼いたくなる。
それがしかも天草大王だったら、私はもう毎日その羽を磨いて
後を追って抱きしめちゃうかも知れない。
宮家は飼っている鶏なんかは当然食さないのだろうけど
卵くらいは食べてるかも知んないので
卵油としても売り出されているほどの天草大王の卵の栄養で
すくすくと元気に鳥を愛される宮として
育っていただきたいと思う、今日この頃なのでした。
追記:
フィギュアスケートを励まれている佳子様も素敵ですが
眞子様の絵画の腕は相当だということです。
それもそのはず、紀子様の祖母である川島紀子様(いとこ様)はパステル画の巨匠だし(豪傑な女才でも有名)、
前田青邨や平山郁夫を師とした香淳皇后は
プロ並の日本画家であったので、やはりその血が流れているのでしょう。
秋篠宮の名前の由縁も、このプリンセスの中に今はまだ蕾として
ぎゅっとつまっているのだと思います。
眞子様が今小さな命たちに愛情をいっぱいうけてお育ちになられて
どんな動物の絵を描かれるようになるのか非常に楽しみです。
川島紀子と小和田雅子の名前について。
か わ し ま き こ
× × × × ×
お わ だ ま さ こ
/と\にそって前から呼んでいってみてください。
もののみごとに「かわしまきこ」「おおわだまさこ」となります。
皇室の結婚はすべて占いで決められており、その結果として、このような一致がうまれるのだそうですが
私はなんとなく川島家という会津藩主の流れをくむものが
とうとう男児親王をお生みになるまでにいたったことの
歴史の運命みたいなものを感じますけどね。
もしくはやっぱり見た目とおりラブラブの
恋愛結婚ととっていいのでしょうか。
紀子様のほんわかした目じりを細めた微笑を見ていると
このひとは本当に幸せなんだって、
女として母として、愛されていlきているんだって
そうロマンチックに考えたいものです。