8Dec

道山ケイです。本日は中2、中3の子向けに高校受験の勉強方法と学習スケジュールについてまとめようと思います。今どの段階なのかを自分でチェックして、これからやるべきことをしっかりと理解し実践していくようにしてください!
目次
中1の子はまずは定期テストで点数を取ろう!

偏差値70以上の高校を目指していく子であれば、
確かに中1から受験勉強をしていった方が
合格率は上がると思います。
ただ私の感覚だと、
中1と言う時期は最低限、
定期テストの勉強だけはしっかりやって、
それ以外は部活や遊びに力を入れた方が、
結果として合格率は上がると思います。
なぜなら、この時期に遊んでおかないと、
後で「勉強せずに遊びたい」と思ってしまうからです。
その結果受験直前になって遊んでしまい、
合格率が大きく下がります。
まだ中学生が始まったばかりの1年生は、
部活と遊びと学校に慣れることだけを
意識すれば十分だと思います。
中2の場合の受験勉強スケジュール

中学2年生になると少しずつ、
受験勉強を始めていかないといけなくなります。
ただここでも2年生の12月ごろまでは、
部活や文化祭などに集中した方が良いです。
なぜなら中2という時期は、
中学校生活の中で最も充実した
1年間になるからです。
部活でもレギュラーになる子が出てきたり、
文化祭でも歌を歌ったりする子が出てきます。
ある意味受験勉強前の最後の楽しい時間とも言えるので、
悔いがない程度まで遊びましょう。
そして文化祭などが終わり、
3学期になったら一気に受験勉強に、
舵を切っていきましょう。
では中2の3学期にやる受験勉強は
何かと言うと、この時期にやるべきことは次の2つです。
1,2年生の数学と英語の復習

まずは1,2年生の
数学と英語の復習をしましょう。
この2つの教科と言うのは
復習するのに時間がかかります。
だから早い段階で始めていかないと
後で絶対に時間が足りなくなります。
復習方法は後ほど紹介するので、
その方法で早め早めに進めて行きましょう。
問題集の選定と勉強計画

これから長い長い
受験勉強に入っていくわけですが、
そこで大事なのが1年以上使っていく
参考書や問題集を決めることです。
具体的な決め方については、
教科ごとの勉強法の部分を参考に
して頂きたいのですが、
大事なことは、
後で変えることがないように、
しっかりと納得する問題集と参考書を
選ぶようにすることです。
また1年間の学習スケジュールも
この時期に大雑把に決めておくと良いでしょう。
- 1日何時間程度勉強するのか
- 春休みや夏休みなどは何をするのか
- 定期テストの学習との兼ね合いはどうするのか
中3の子が意識すべき学習スケジュール

3年生になるといよいよ本格的に
受験勉強がスタートしてきます。
ここで意識すべきことは、
次の3つです。
学習計画を再度見直そう

2年生の3学期に作った学習計画を見て、
それが自分に合っているかを見直す
ということになります。
当時はまだあまり深いことは考えずに、
1日3時間勉強する!みたいな感じで、
学習計画を作っていると思います。
その結果、
「1日3時間も勉強するのが無理だった」
と考える子も出てきます。
であれば、
このタイミングでもう一度、
学習計画を立て直すようにしましょう。
受験勉強を開始して
3ヶ月くらい経っているので、
自分自身の集中力などは、
だいたい理解できていると思います。
その感覚を意識して、
学習計画を立て直してください。
なおこの時、この後説明する、
教科ごとの勉強方法を参考にしてください。
12月になったら過去問を解こう

基本的に3年生の11月ごろまでは、
この後説明する教科ごとの勉強法を
ひたすら行っていくことになります。
その後12月になったら、
必ずやってほしいのが「過去問を解く」ということです。
なぜなら受験勉強と言うのは、
学校や都道府県ごとに傾向が異なります。
今まで中学校で受けてきたテストと比べ、
問題の出し方が少し変わっていたりするので、
それに慣れる必要があります。
そこで過去問を必ず解くようにしてください。
1月になったら面接練習をしよう

また1月になったら面接練習をしましょう。
学校によって面接試験がないところもありますが、
もし面接試験があるなら
ここはしっかりと対策をしましょう。
なぜなら私たちが思っている以上に、
配点が高いからです。
どれだけ偏差値や内申点を上げても
ここで手を抜くと受験には合格できません。
学校の先生やお父さんお母さんと
協力をしながら対策を進めましょう。
国語の受験勉強は過去問が重要!

国語の受験勉強で最も大事なことは
基礎を固めることと過去問を解くことになります。
この勉強方法を間違えると、
どれだけ勉強しても偏差値が上がらず
受験が失敗に終わります。
後で後悔する前に
この方法で進めるようにしてください。
ステップ① 過去問をしっかり解こう

まずやるべきことは過去問を解くことです。
中3の受験勉強スケジュールのところで、
過去問は12月になったらやろう!
と書いたのですが国語だけは別です。
夏休み頃になったら、
もう過去問を解き始めてOKです。
なぜなら国語は過去問を解くことで、
長文読解の力が付くからです。
最低でも3年、できれば10年くらいは
過去問を解くようにしましょう。
これで最低限の長文読解能力が付きます。
ステップ② 漢字と文法をマスターする
次にやってほしいのは、
漢字と文法という2つの基礎を
しっかりと固めることです。
この2つはきちんと勉強をすれば、
確実に点数が取れる部分になります。
漢字は高校入試の漢字が
まとまっている参考書が書店に売っているので、
それを1冊買ってきてひたすら覚えましょう。
文法は高校入試対策の問題集を1冊買ってきて、
それを最低でも2回は繰り返しましょう。
その後でよくわからないところは、
学校の先生や塾の先生に教えてもらいましょう。
ステップ③ 長文読解の力をパワーアップさせよう

最後にやるべきことは、
長文読解の力をひたすらパワーアップ
させていくということです。
高校入試国語の場合、
結局最後は長文読解で何点取れるかが
勝負になります。
ではどうしたら
長文読解の力が付くのかと言うと、
ひたすら長文読解問題を解くことになります。
ステップ1で過去問は解いていると思うので、
最低限の力は付いていると思います。
ただこれだけではまだまだ甘いです。
追加で書店で専用の問題集を買ったり、
塾の問題集を使って、
毎日1問は長文読解の問題を解く!
くらいの覚悟で進めて行きましょう。
100問くらい解けば、
読むスピードが速くなり、
パターン認識ができるようになるので、
一気に偏差値が上がります!
社会の高校入試対策のまとめ

社会の受験勉強というのは、
とにかく短期間で偏差値が上がるので、
中3の2学期からはじめても結果が出ます。
今全く受験勉強をしていない
と言う場合は社会だけに絞って、
勉強をしていくというのもおすすめです。
ステップ① ひたすら語句を頭に叩き込もう!
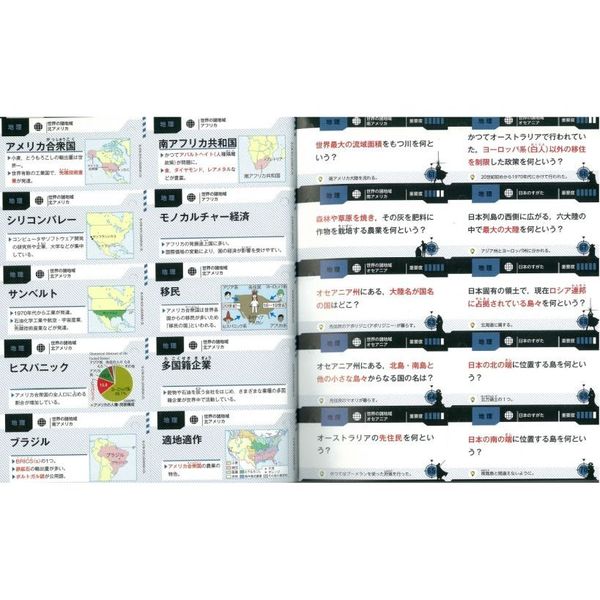
受験勉強を始める時期にもよるのですが、
社会の学習の基本は「暗記」です。
つまり語句をしっかりと覚えることで、
簡単に偏差値を上げることができるのです。
ではどうしたら語句を覚えられるのかというと、
問題集を繰り返し解くに尽きます。
- 学校で使っている問題集
- 書店に売っている受験対策問題集
- 塾で配布された問題集
あなたが一番使いやすい
と思うもので良いので、
とにかくひたすら問題集を解いてください。
今まで定期テストのたびに、
しっかりと語句を覚えてきた子であれば2回、
いつもうろ覚えで進めてきた子であれば4回は、
問題集を解き直すようにして下さい。
ステップ② 過去問を3年解こう!
次にやるべきことは過去問を解くことです。
過去問を解くことで都道府県ごとの傾向が
つかめたり、覚えられていない部分がわかります。
またグラフ問題などの、
覚えるのではなく理解する問題を
解いていく力が身につきます。
国語ほど重要ではないので、
時期としては12月に入ってからでOKですが、
最低3年分は過去問を解くようにしてください。
ステップ③ 苦手分野を再度暗記しよう

過去問を解くことで見えてきた、
自分の苦手な部分を再度覚え直しましょう。
歴史が苦手な子であれば、
再度歴史の部分のみ
問題集を解き直しましょう。
地理のグラフが苦手な子であれば、
グラフの問題を繰り返し解きましょう。
苦手分野が克服できれば、
10~20点くらいアップできます。
数学の偏差値アップで大事なこと

数学の偏差値を上げていくステップは、
本当に時間がかかります。
時間がかかるからこそ、
きちんと中2の冬から受験勉強を
進めてきた子でないと思うように上がりません。
逆に中2の冬からしっかりと対策をしてきた子は、
他の子と一気に差を付けることができる教科なので、
これから受験勉強を始める子は、
気合を入れてこの記事を読んでください。
ステップ① 基礎問題を繰り返そう

まず最初にやるべきことは、
学校の問題集でも受験対策の問題集でも
塾の問題集でもどれでも良いので、
最低2回繰り返すことです。
しっかりと定期テストの時に、
勉強をしてきた子であれば、
2回繰り返せば公式などが思い出せます。
もし今までサボってきた子であれば、
わからない部分を家庭教師の先生などに
サポートしてもらいながら、
一つずつ解けるようにしてください。
偏差値50以下の学校を狙うなら、
おそらくステップ1だけで、
受験勉強が終わってしまうと思います。
それくらいこの部分は、
面倒で時間がかかる部分です。
でもそれくらい効果が高い勉強方法なので、
手を抜かずしっかりとやるようにしてください。
ステップ② 応用問題を解こう

偏差値50以上の学校を目指す子は、
基礎の問題集が解けるようになったら、
ワンランク上の問題集を解きましょう。
※偏差値50以下の学校を目指す子は、
この部分は飛ばしてください。
おそらく基礎問題集ができるのは、
中3の夏か秋ごろだと思います。
だから受験本番まで残り半年くらいだと思います。
時間を考えると、
多くて2回、もしかしたら1回しか
問題集ができないかもしれません。
それでも仕方がないです。
1回でもハイレベルな問題に触れておくことで、
テスト当日に同じような問題が出てきたときに、
解き方の流れがイメージできます。
一度も解いたことがない状態だと、
おそらく何から手を付けたらよいのか、
わからなくなってしまいます。
だから覚えようとするのではなく、
ハイレベルな問題に慣れるという目的で、
ワンランク上の問題集を解くようにしてみてください。
ステップ③ 過去問を解こう
最後に過去問を解きましょう。
時期としては12月頃で大丈夫です。
過去問を解く目的は問題に慣れることと、
苦手分野を探し出すことです。
ここで見つかった苦手分野については、
その後の1か月で徹底的に対策をしてください。
理科はこの問題集を使って合格をつかみ取ろう!

理科の受験勉強法も
社会とほとんど同じです。
1冊問題集を決めて、
それをひたすら繰り返すことになります。
ただ社会の勉強法の時には、
問題集の選び方について、
あまり詳しく触れていませんでしたので、
ここでは少し問題集の選び方にも触れていきます。
ステップ① 使いやすい問題集を選ぶ

高校受験の勉強を進めて行くうえで、
問題集選びは非常に重要です。
なぜならここを間違えると、
結局入試本番までに時間が足りなくなり、
全ての範囲を覚えることができなくなるからです。
では問題集はどういった基準で、
選んでいったらよいのかと言うと、
子どものレベル(偏差値)にあったものを
選ぶのが大事になります。
偏差値60くらいの子であれば、
分厚くて細かいところまで掲載されている
ハイレベル問題集を使ってOKですが、
偏差値40の子が上記の問題集を使っても、
おそらくわからないところだらけで、
時間がかかりすぎてしまうわけです。
この場合は、ペラペラで良いので、
きちんと繰り返し学習できるレベルの、
問題集を選ぶのが良いです。
もちろん学校の問題集でも大丈夫です。
ステップ② 問題集を繰り返し解く

自分に合う問題集が決まったら、
後はそれをひたすら解いていきましょう。
最低でも2回、できれば4回は解きましょう。
理科の場合社会と違って、
多少計算問題が出てきます。
もしわからなければ、
きちんと解けるようになるまで、
先生に教えてもらってください。
わからないまま放置しておくと、
そこで点数が頭打ちになってしまいます。
ステップ③ 過去問+苦手分野補強

12月になったら過去問を解き、
そこで出てきた苦手分野を補強していきましょう。
この辺りは社会と同じ流れになります。
あと理科の場合は、
過去問を解きながら、
「わからない問題はどんどん飛ばす」
という練習をしてください。
苦手分野に時間を取られると、
せっかく取れるはずだった得意分野で、
点数を落としてしまう可能性があります。
これは注意するようにしてください。
英語の高校受験勉強法

英語の学習方法は国語と似ています。
ただ普段使わない言語なので、
若干勉強の流れが異なるので、
その部分をしっかりとまとめます。
ステップ① 英単語と英熟語を覚える

英語は普段使わない言語です。
だから最初に英単語と英熟語を
しっかりと覚えるようにしてください。
これをしていかないと、
結局文章自体の意味が分からないので、
問題の解きようがないのです。
ただここで一つ大きな問題があります。
中学生が高校入試までに
覚える英単語は約1500、
英熟語は約500あります。
つまり1年間で覚えようと思ったら、
1日5個ずつは覚えていかないと
いけないわけです。
さすがに毎日は厳しいと思うので、
休む日も入れることを考えると、
どうしても1日10個くらいは覚えていかないと
間に合いません。
ですのでできる限り、
中2の冬から始めるようにしてください。
ステップ② 文法問題を解いていく
ステップ①と並行して進めてほしいのが、
文法問題を解いていくというステップです。
いくら英単語と英熟語を覚えたとしても、
最低限の文法を理解していないと、
文章を読むことができません。
書店に売っている問題集でも、
学校で使っている問題集でも何でも良いので、
一つも英語の問題集を最低2回は、
解き直すようにしてください。
ここまでのステップを、
できれば中3の8月までに終わらせてください。
ステップ③ 過去問を解く

最後は過去問です。
過去問をたくさん解いて、
長文読解力を付けていきましょう。
時期としては、
中3の9月ごろから始めてください。
そしてもし長文が解けないことが分かったら、
ひたすら長文読解だけが集まった問題集を
繰り返し解くようにしてください。
国語と同じで、
最後は長文の勝負になるので、
ここはできる限り時間をかけていくと良いです。
定期テストが一番大事

ここまでお伝えした方法を実践すれば、
基本的な受験勉強はできると思います。
ただ最後に一つ大事なことをお伝えします。
受験勉強以上に大事なことは、
定期テストの勉強をしっかりする!
ということです。
中3になると、
受験勉強ばかりに意識がいってしまい、
定期テストの学習を疎かにする子が多いです。
しかしこれは本末転倒です!
なぜなら中3の定期テストに出る内容は、
そのまま受験にも出るからです。
また定期テストで点数を取れば、
内申点が上がるので、
高校入試の合格率も大きく上がります!
だから一石二鳥なのです。
必ず、
一番優先するのは定期テストの勉強、
余った時間で高校受験の勉強を
するようにしてください。
なお効率の良い定期テストの勉強法や、
子どもの勉強に対するやる気を引き出す方法、
効率良く英単語や社会の語句を暗記する方法などは、
「道山流!成績UP無料メール講座」で解説しています。
7日間のメール講座と言う形で、
毎日一つずつステップバイステップで上記の点を、
解説していく講座(最初から最後までずっと無料です)なので、
よかったらこちらも読んでみてください。
>>成績UP無料メール講座の公式サイト
関連記事
子どもの成績を短期間で上げたいお母様へ
コメント
この記事へのトラックバックはありません。









この記事へのコメントはありません。