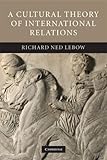今日の横浜北部は朝からすっきりしないお天気でした。昼以降はけっこう寒くなりましたね。
さて、前回のエントリーの続きです。
次に出る本の第一章なのですが、実際に本に載せるかどうかはさておき、一応「先行研究」(literature review)のようなことをここでやってみたいと思います。
私は日本の地政学について研究したわけではないのですが、とりあえず日本語で「地政学」というタイトルのついた本について、前回に提示した3分類で大まかにわけて、それぞれに寸評を加えてみたいと思います。
===
日本で出ている「地政学」というタイトルのついた本で、しかも学問としての地政学と関連性が高いと思われるものをリストアップしておきたい。
ただし以下に挙げるリストを私自身も完全なものとはいえず、あくまでも私が手にしたことのあるものばかりなので、公平ではないと感じるかたもいらっしゃるかもしれないので、あらかじめご容赦いただきたい。
前回のエントリーでは
①:政治地理系の地政学研究(批判地政学、ポスコロ系、ジェンダー系、哲学系)
②:戦略系の地政学研究(古典地政学・伝統地政学、怪しい陰謀系も含む)
③:国際政治系(新地政学?)
という3つの分類の枠組みを提示したが、まずはこれに沿ってリストアップしていきたい。
〜〜〜
①政治地理系
ー『
現代地政学入門』 by コーリン・フリント
政治地理学系の入門書のひとつ。日本の第一人者である高木彰彦九州大学教授の翻訳。編訳者の解説で私の名前が解説に出てくるが国際関係論の理論には詳しくないようでやや残念。新しい地政学の構築を狙っている?
ー『
地政学とは何か』byクラウス・ドッズ
オックスフォード大学出版の「超短い入門」シリーズからの翻訳。批判地政学の立場からの解説が中心。個人的には原著の内容にまとまりがなく、網羅的なだけで質は低いと考えている。
ー『
国際関係の政治地理学』by横山昭市
スタンダードな地理学によって国際政治の事象を分析したもの。批判地政学などの新しい動向についての言及はなくて全体的に古い印象だが、鉄道や石油に関する具体的な事例に触れていて個人的には役立つものと認識。ただし著者がだいぶお年のようで続編がなさそうなのが残念。分類的には②にも近いか。
ー『
日本の政治地理学』by高木彰彦(編)
99年の本なので古いが、日本の政治地理学の一つの到達点か。最初の2つの章はそれまでの内外の政治地理学の動向を知る上では貴重。
ー『
帝国日本と地政学』by柴田陽一
若い研究者による学術本。京都大学の小牧実繁教授を中心に、満州で活躍した地理学者など、戦前の「日本地政学」の成り立ちや人脈、それに背景について論じたもの。文献的にも非常に貴重。最後の講演録に私の名前も出てくる。値段が高いのが難点。批判地政学に興味ある様子。
ー『
入門 国境学 - 領土、主権、イデオロギー 』by岩下明裕
タイトルに地政学とは入っていないのでこのリストの中では例外的な存在だが、きわめて批判地政学的なアプローチを活用しているのが特徴。最近の日本の政治地理学の状況を簡単に教えてくれるという意味で貴重。ただし視点はあくまでもボトムアップ的で、トップダウン型の古典地政学系に対して批判的。
②戦略系
ー『
地政学入門』by曽村保信
戦略系ながら比較的中立的な立場で書かれた概説書で、入門書としてもいまのところは決定版といえるかもしれない。ただし読後に明確な視点が得られるかといえば微妙。とにかく時代遅れになっている部分が大きい。私が書こうとしているのはこれの続編。
ー『
世界史で学べ:地政学』by茂木誠
予備校の世界史の先生が書いた、世界史を古典地政学的観点から分析したもの。理論への言及は物足りないし、やや断定的な論調は気になるが、「入門の入門」としては計算してよく書かれている。本ブログや私の書籍に言及してくれていてありがたい限り。
―『
進化する地政学』&『
胎動する地政学』byグレイ&スローン
戦略系学者たちによる決定的な論文集。すでに古くなっているが文献的には貴重なものばかり。残念ながら絶版で復刊の予定もなし。
ー『
マッキンダーの地政学』by H.J.マッキンダー
ご存知「近代地政学の祖」であるマッキンダーの基礎論文集。翻訳は「地政学入門」の故・曽村氏。ただし本文の中に決定的な訳語の間違いがあり、その修正を原書房の社長に直訴したがスルーされたのが残念。将来的には私が正確な訳を出したいが・・・
ー『
平和の地政学』byニコラス・スパイクマン
これも基礎文献。本当は主著の『
America's Strategy in World Politics』を訳したかったが分厚すぎて断念。いつか挑戦するつもり。
ー『
マハン海上権力論集』by麻田貞雄
マハンの基礎文献を網羅したダイジェスト版。主著の「海上権力史論」だけでなく、地政学的な世界観を示した「アジアの問題」なども要約版で収録。解説も秀逸。
ー『
地政学の逆襲』byロバート・カプラン
ここ数年間で訳出された地政学本の中ではもっとも質の高い本。原題は「地理の復讐」だがスパイクマンからマッキンダーまで古典地政学の論者たちのアイディアが頻繁に使われており、現地取材と共に培った知識で世界を大きく概観していて興味深い内容に仕上がっている。
ー『
地政学で世界を読む―21世紀のユーラシア覇権ゲーム』byZ・ブレジンスキー
戦略系の地政学の一つの頂点。ただし状勢をあまりにも静的にとらえているために批判されやすいか。マッキンダーの名前を間違えているのはご愛嬌としても、アメリカ政府のアドバイザーのリアリスト的な思考を垣間見せてくれるという意味でとても価値のある本。絶版が惜しまれる。
ー『
100年予測』byジョージ・フリードマン
元祖リスク・アナリストの主著ともいえる未来予測シナリオ本。地政学の理論への言及はかなり少ないが、アメリカの大戦略の大前提がさらっと書いてあって参考になる。ただし学術書ではないのでアカデミック界からは評価されていないのが難点。基本的にアメリカ万歳。
ー『
地政学で読む世界覇権2030』byピーター・ゼイハン
同上。地政学理論そのものへの言及はないが、地理と国際政治における戦略についての関係から未来予測的なことを行っている。アメリカ万歳。
ー『
悪の論理』by倉前盛通
80年代に日本に第二次地政学ブームをつくった記念碑的な本。ただしやや陰謀チックで学術的なものとはいえないのが玉にキズ。政治地理系の人々は「地政学の誤解をさらに招いた本」としてよく批判される
―『
地政学の論理』by中川八洋
ネオコン的視点から書かれた、政治的に非常に偏ったタイプの英米系地政学論の概説書。よく調べてあるとは思うがスパイクマンがコミンテルンのスパイだったアシスタントに毒をもられて殺されたという憶測を引用なく書いているところなどはかなり疑問。私に対する的外れな批判もあり。対人攻撃がお好きなようで、これでよく国立大学の教授が務まったなと感心するほど。倉前本と同様に誤解を招くパターン。
ー『
地政学の罠にはまった日本近現代史』(全2巻)by森田徳彦
タイトルの通り、日本の近現代史を地政学的観点から分析した本。学術本の体裁をとっているが、引用されている論文などにかなり思想的に偏りがあって微妙であり、まるで参考文献の欄に「正論」の執筆陣が揃っているかのような景色が見える。ただし著者のやる気だけはヒシヒシと感じる意欲作。
ー『
地政学入門』by河野収
これも古い入門書だが、曽村本よりも地理そのもに焦点を当てたもの。きわめて中立的にフラットに書かれている。大陸系と海洋系という二つの分類を示したのは一つの功績か。ただし防大の教科書的な意味合いが強い印象があり、やや退屈な印象も。
―『
地政学は殺傷力のある武器である』by兵頭二十八
非常に軍事戦略論的なユニークな地政学論の一つの頂点。マッキンダーからハウスホーファーまでポイントを押さえて解説しているが、やはり後半の日本の地政学について論じた部分がユニークで読み応えあり。体系的な入門書ではないが、マニアックな文献への当たり方などは兵頭節炸裂という感じで興味深い。ただしこれも個性が強いのでアレルギーを起こす人がいそう。
ー『
日本人が知らない地政学が教えるこの国の針路』by菅沼 光弘
元公安幹部による暴露的な本。思ったよりは地政学の理論への言及があるが、基本的には日本現代裏歴史・陰謀系か。中で語られているエピソードはどこまで本当なのかわからないが面白いことはたしか。
③国際政治系
ー『
地政学と国際戦略』by浦野起央
国際関係論などを網羅的に記述することで有名な浦野教授による、国際関係における地理的な側面を地政学というスパイスを使って中立な立場から分析しようという試み。それぞれの理論への言及は思ったほど深くはないが、近世の歴史と地理の交差点的なポイントは押さえていて読んでいても安心できる。戦略というよりは安全保障の観点という意味合いが強い。
―『
拡大ヨーロッパの地政学』byモウリッツェン他
デンマークの学者による国際関係論をベースとした新しい地政学構築の試み。ネオリアリズムの「極」という考えではEU内の個別の国家の対外行動は説明できないという問題を出発点として、そのためには「非極」国家である個別の国家の配置(コンスタレーション)を考慮することが重要だと議論。マハンやマッキンダーよりもむしろウォルトやウォルツなどの国際関係論の地政学的な視点を参考にしている。
ー『
感情の地政学』byドミニク・モイジ
国際政治を「感情」というキーワードから俯瞰してみようとする、どちらかといえばジャーナリスティックな提案書。もちろん地政学の理論などは関係なく、題名はキャッチフレーズとして関係あるくらい。地政学=グローバルな政治、くらいの考えか。薄くて読みやすいが・・・。
ー『
21世紀 地政学入門』by船橋洋一
朝日の国際派コラムニストの著者の連載記事をまとめたもの。マッキンダーなどへの言及はほんのわずか。多彩な国際政治の状況の解説書なので、やはり題名やオビの文句はミスリーディング。ただし「国際政治ニュースの入門書」としてはよくまとまった本と言えるかも。
ー『
地政学と外交政策』by 花井等ほか
冒頭で地政学の理論への言及はあるが、どちらかといえば個別の国をそれぞれ解説した国際政治概況的なもの。何しろ情報が古い。
―『
東アジア動乱 地政学が明かす日本の役割』by武貞秀士
これも地政学の理論などにはわずかに言及しているが、主に東アジアの外交・安全保障の関係性に焦点を当てたもの。
ー『
新・地政学 - 第三次世界大戦を読み解く』by山内昌之&佐藤優
前述した船橋本と似たような構成。あまり地政学の理論そのものへの言及はナシ。現在の国際政治の状況の概観としては面白い。
ー『
世界のニュースがわかる! 図解地政学入門』by高橋洋一
これも船橋本と似たタイプ。実際の地政学の理論への言及は少ない。
ー『
地政学リスク』by倉都康行
未読なのでコメント不可。目次だけみると戦略系ではなく、金融系という印象。
ー『
日本表象の地政学: 海洋・原爆・冷戦・ポップカルチャー 』by遠藤 不比人
文学・ポスコロ系の意味不明な使用法の典型的な例。「地政学的磁場」という摩訶不思議な用語。
ー『
視覚都市の地政学』by吉見 俊哉
同上。都市論。「地政学」は単なるキャッチ・フレーズ
====
とりあえず今日のところは以上です。これからも引き続きアップデートしていきます。
▼~あなたは本当の「孫子」を知らない~
「
奥山真司の『真説 孫子解読』CD」

▼~これまでのクラウゼヴィッツ解説本はすべて処分して結構です。~
「
奥山真司の現代のクラウゼビッツ『戦争論』講座CD」

▼奴隷の人生からの脱却のために
「
戦略の階層」を解説するCD。戦略の「基本の“き”」はここから!

▼
奥山真司の地政学講座
※詳細はこちらから↓
http://www.realist.jp/geopolitics.html


 http://ch.nicovideo.jp/strategy2/live
http://ch.nicovideo.jp/strategy2/live
https://www.youtube.com/user/TheStandardJournal